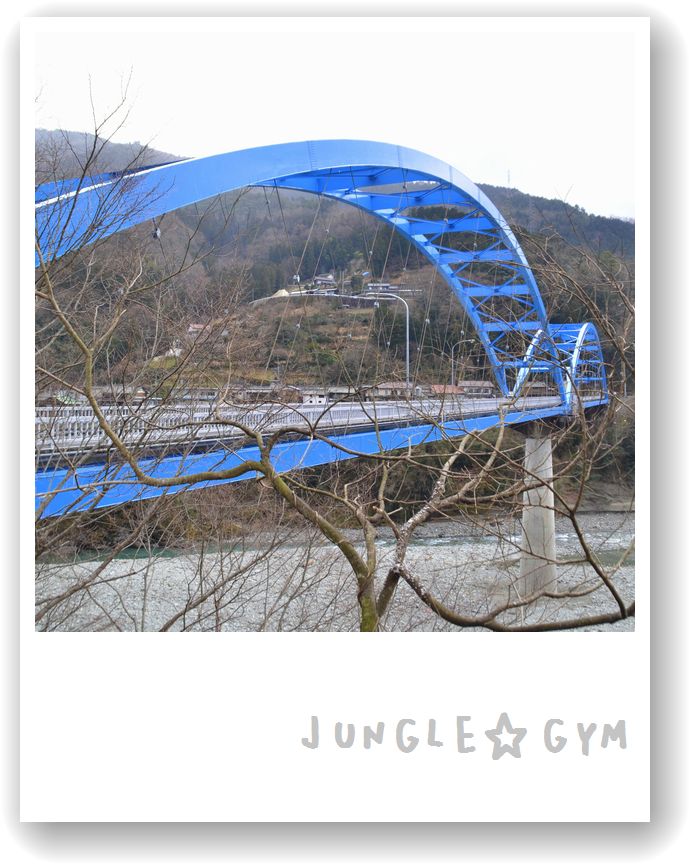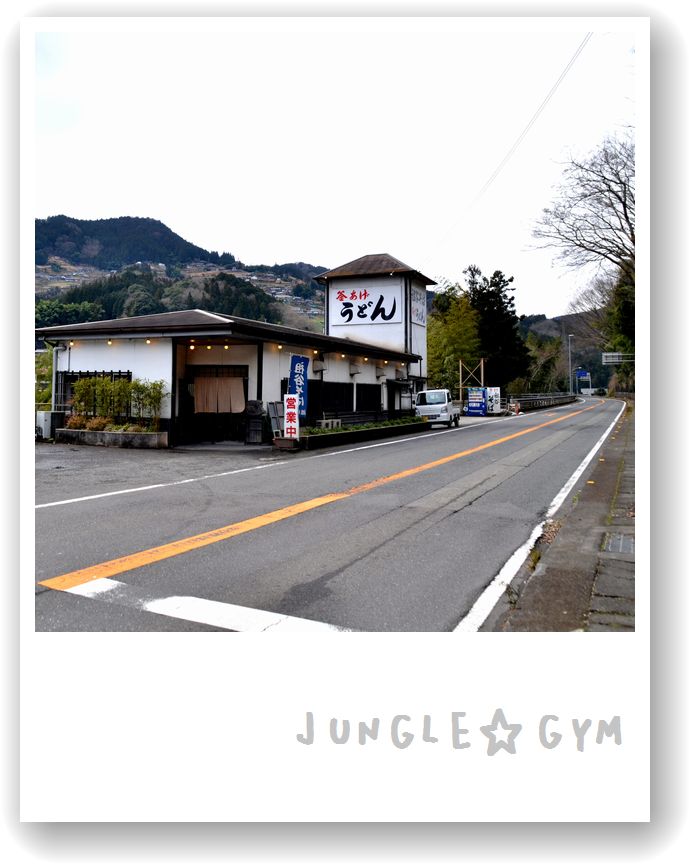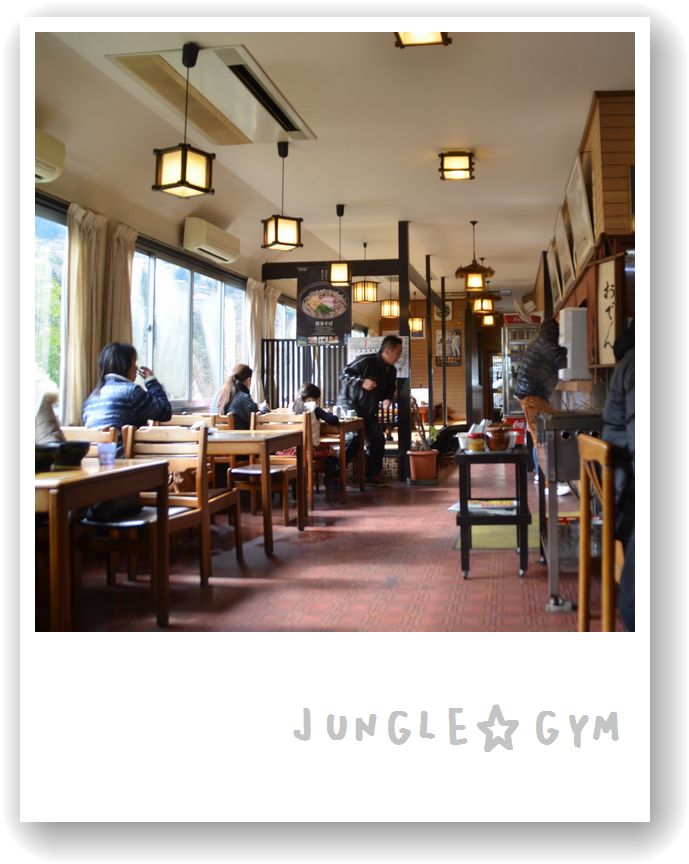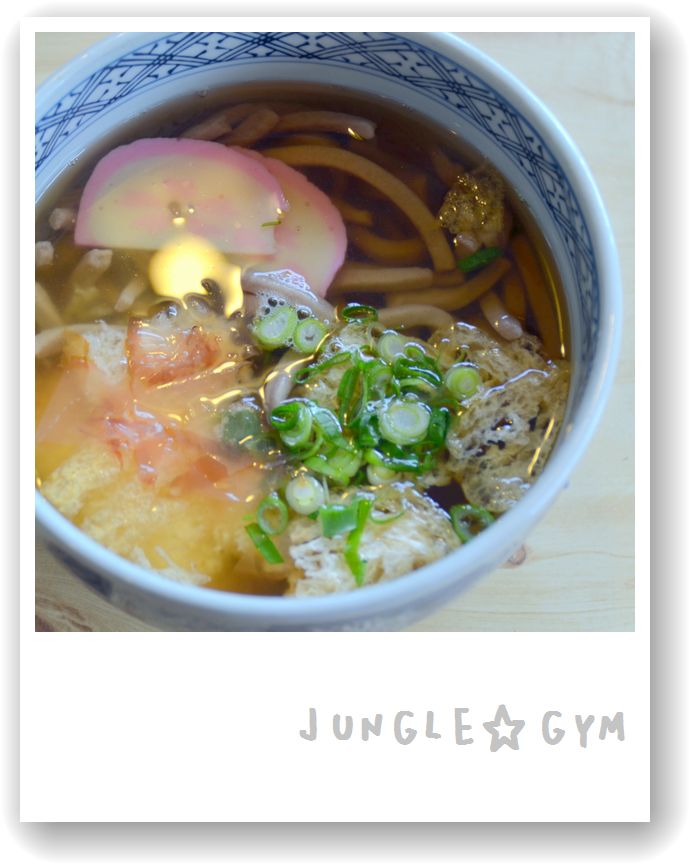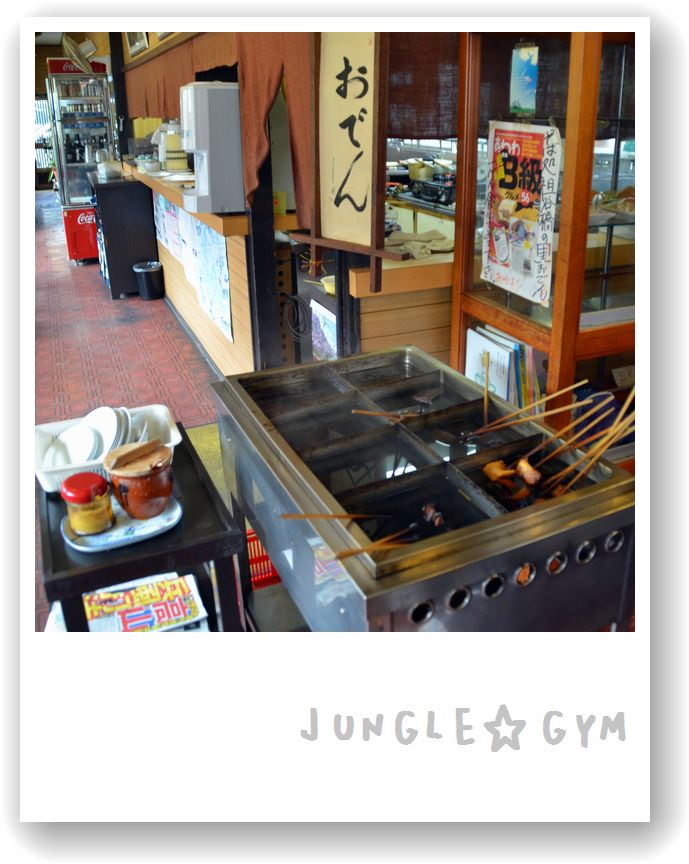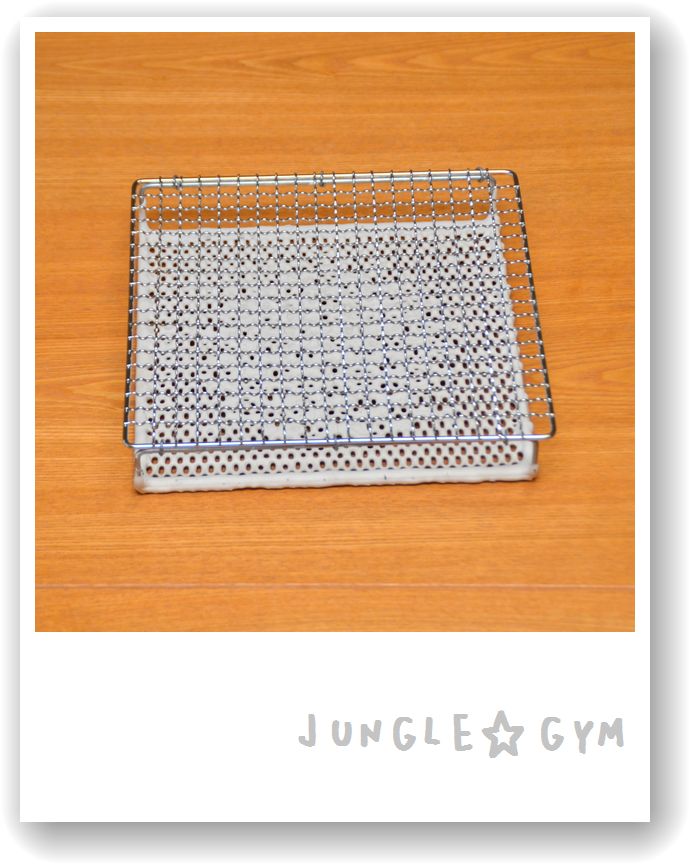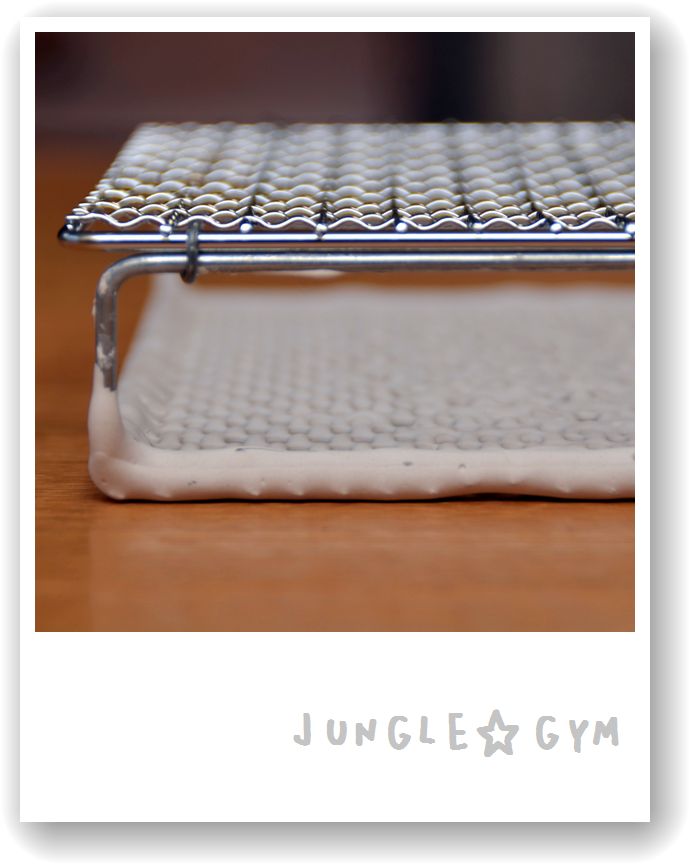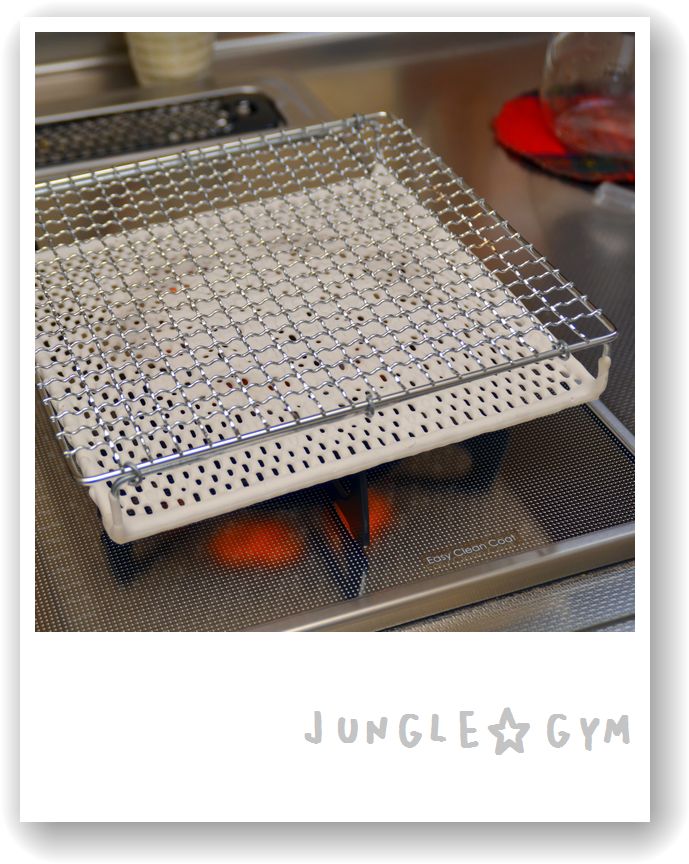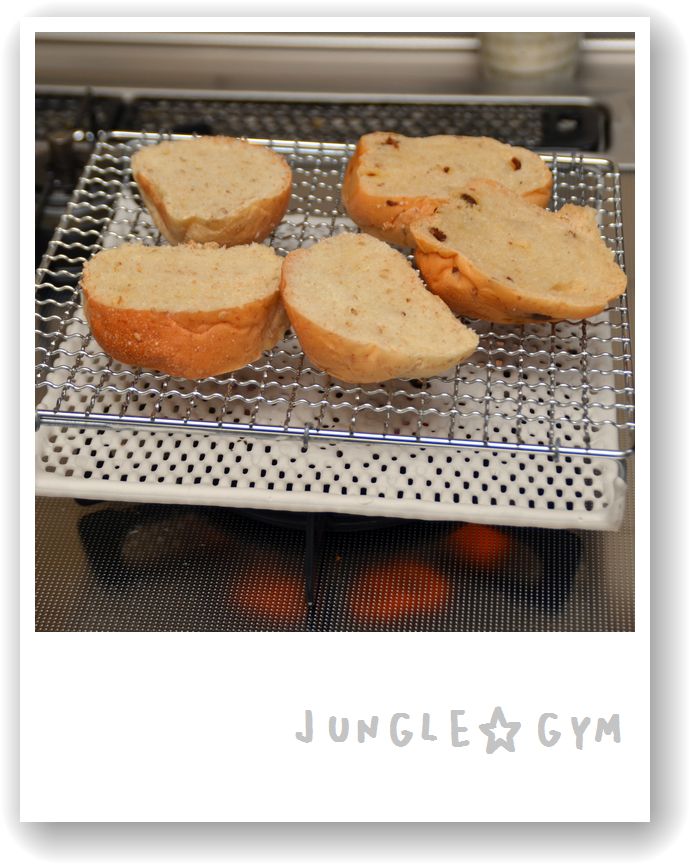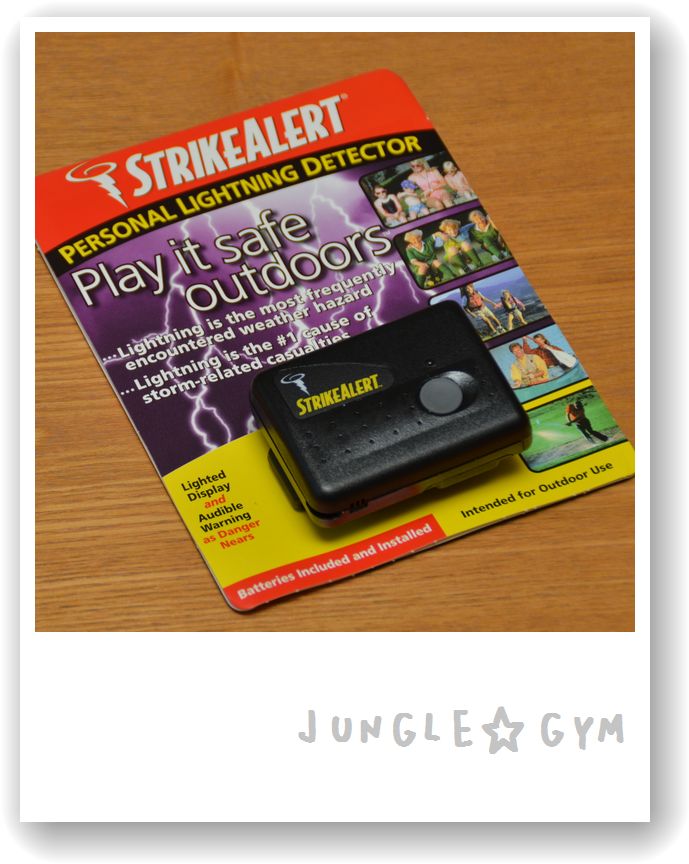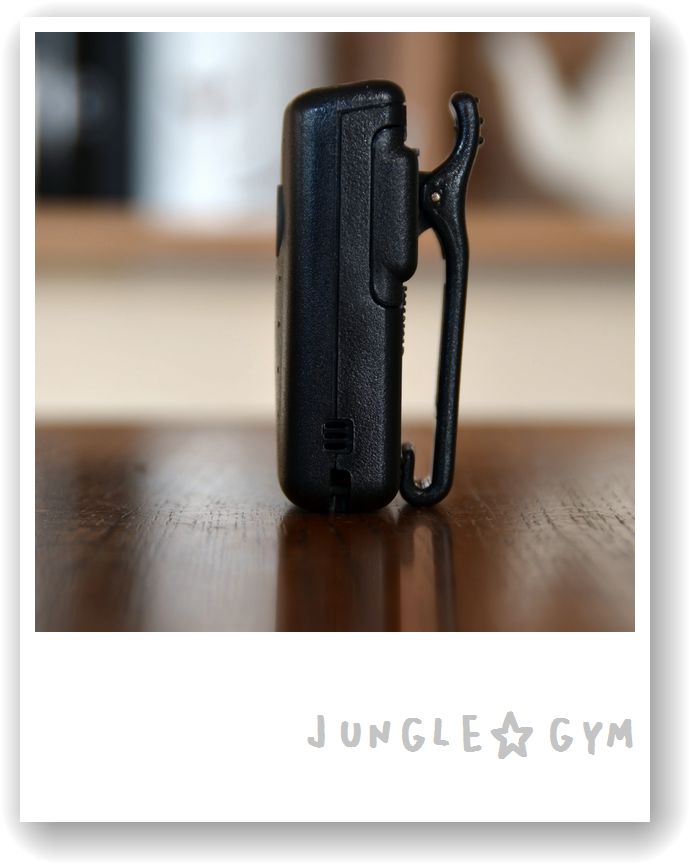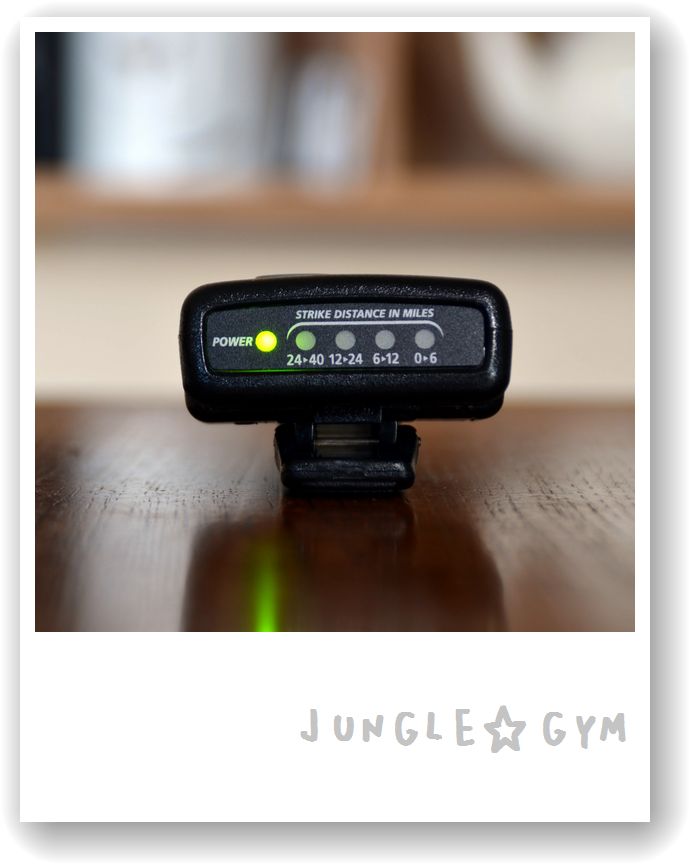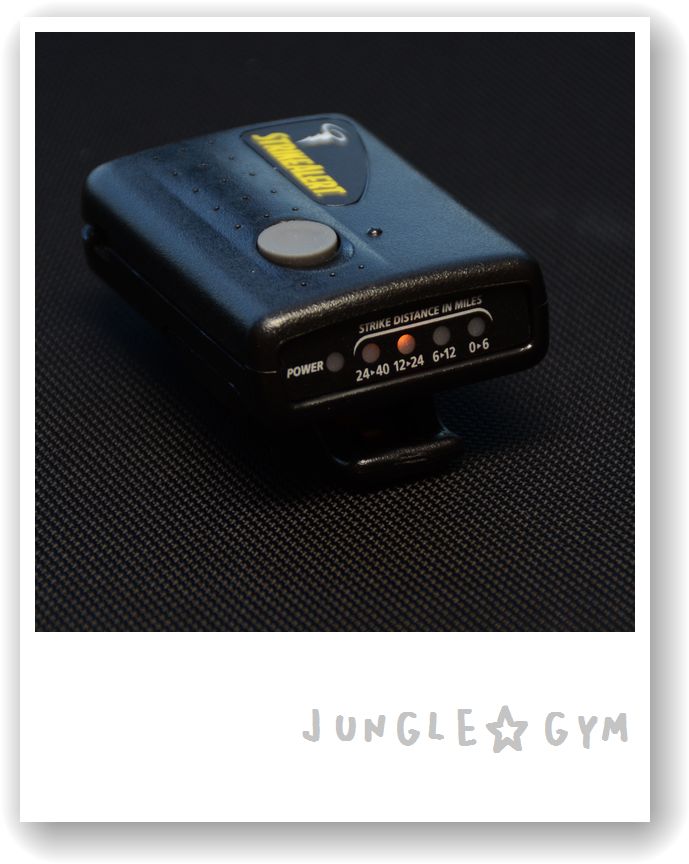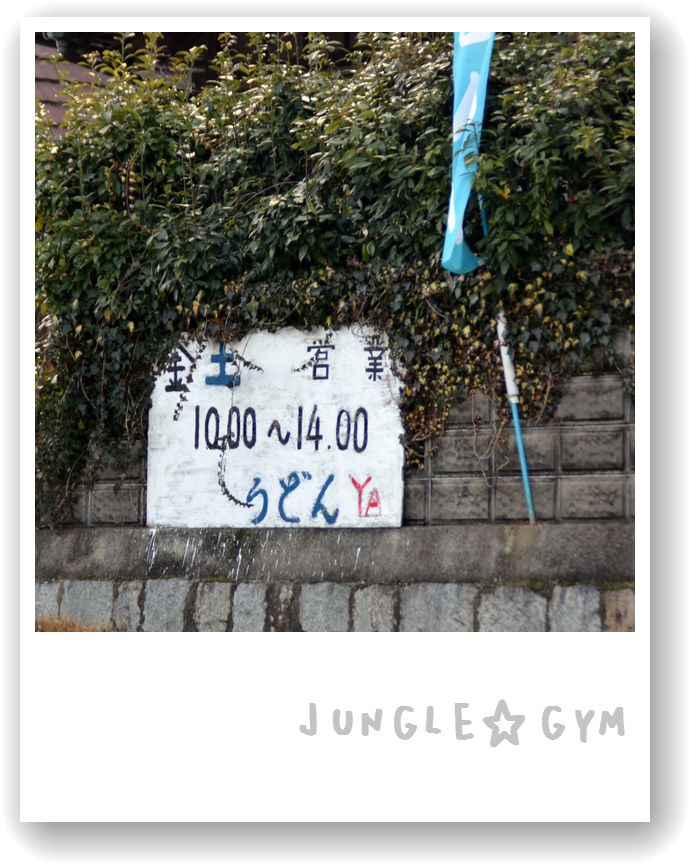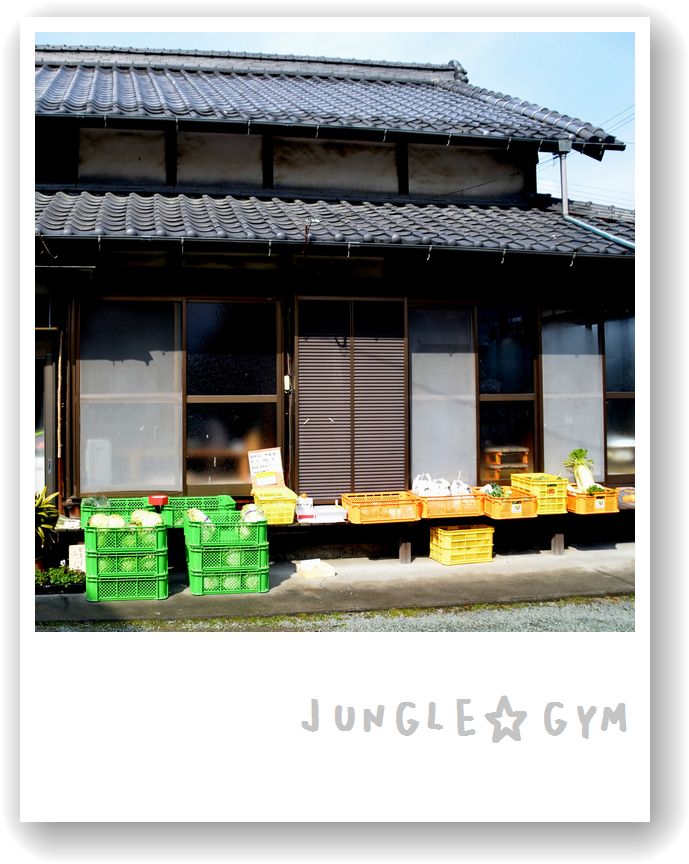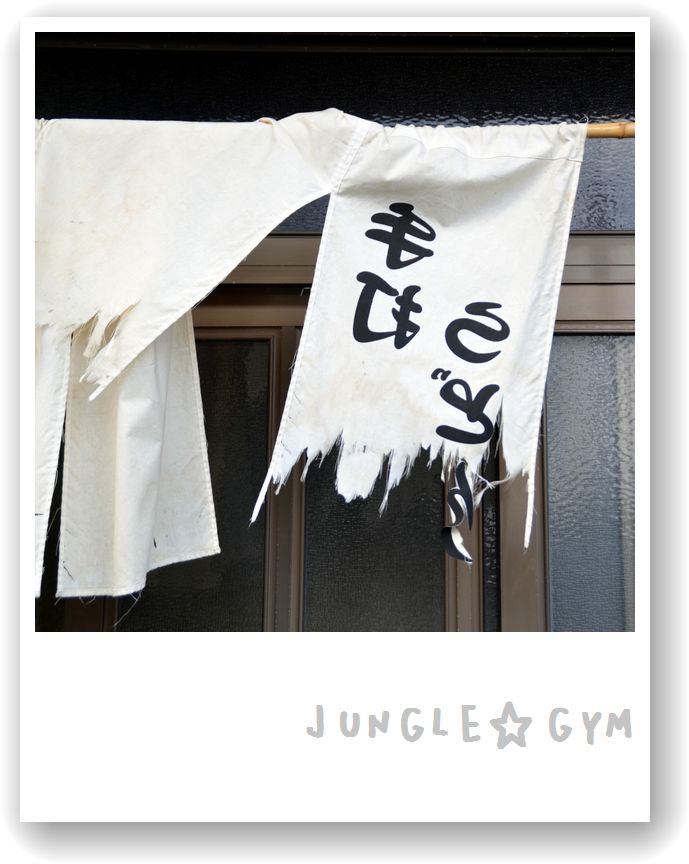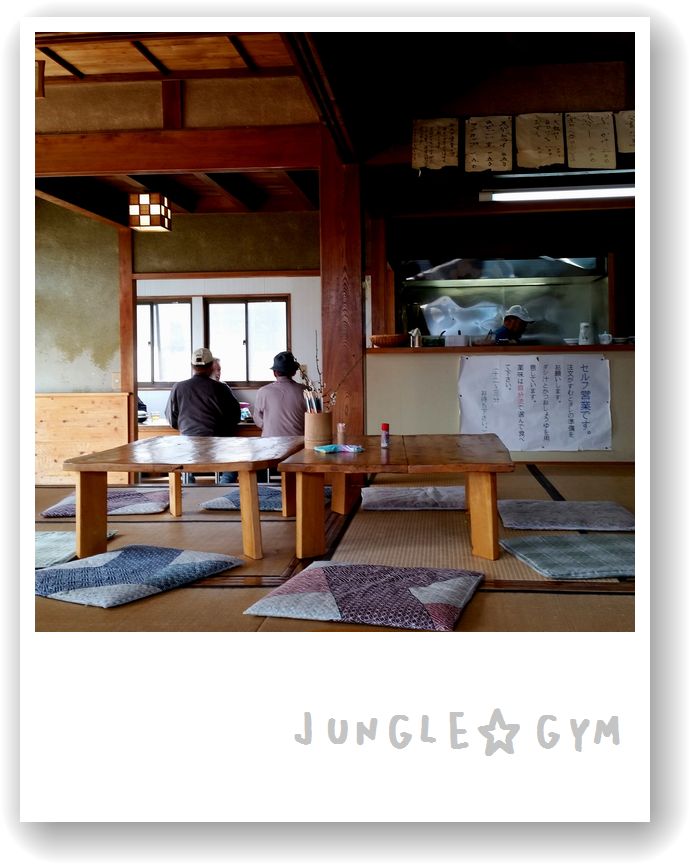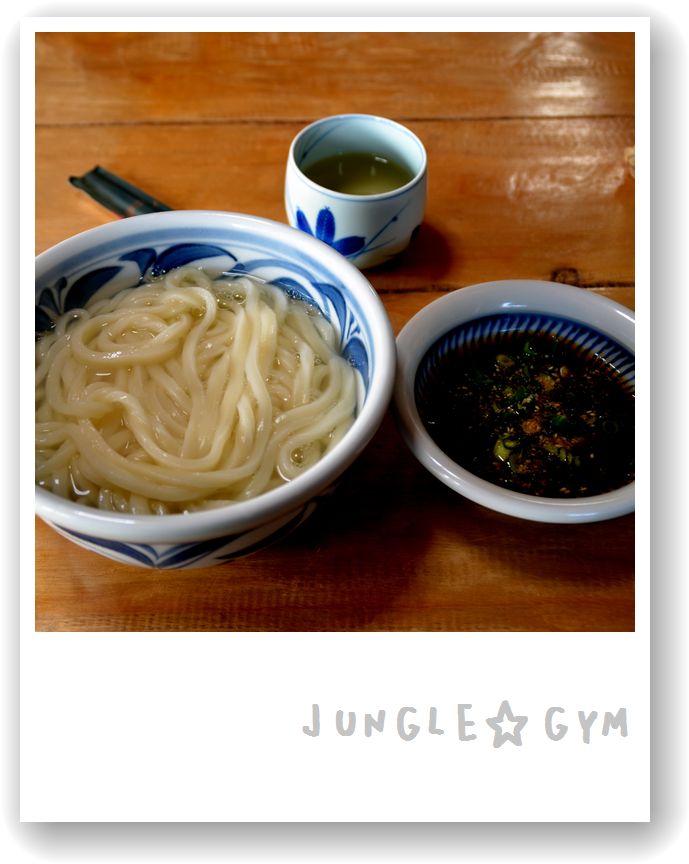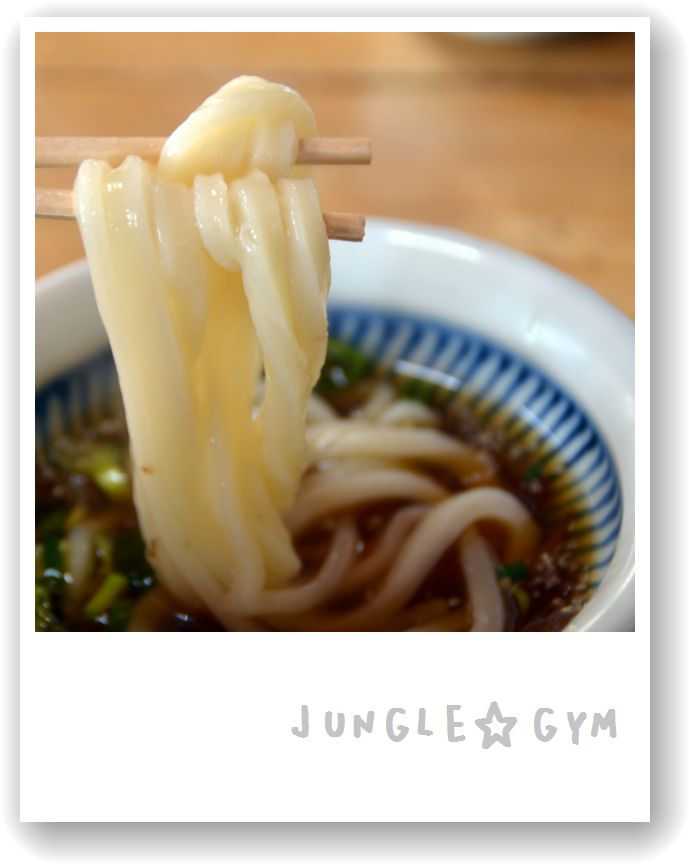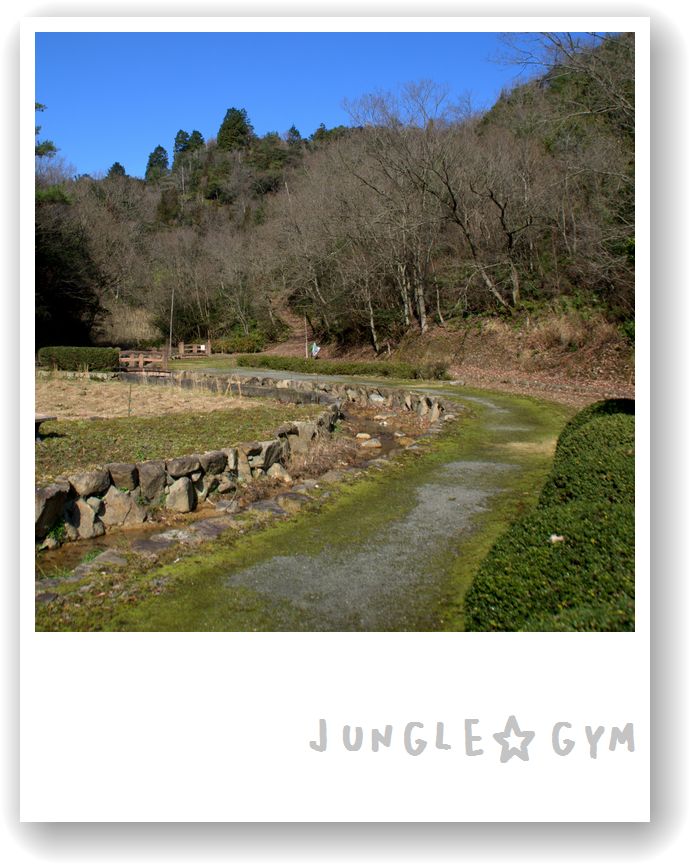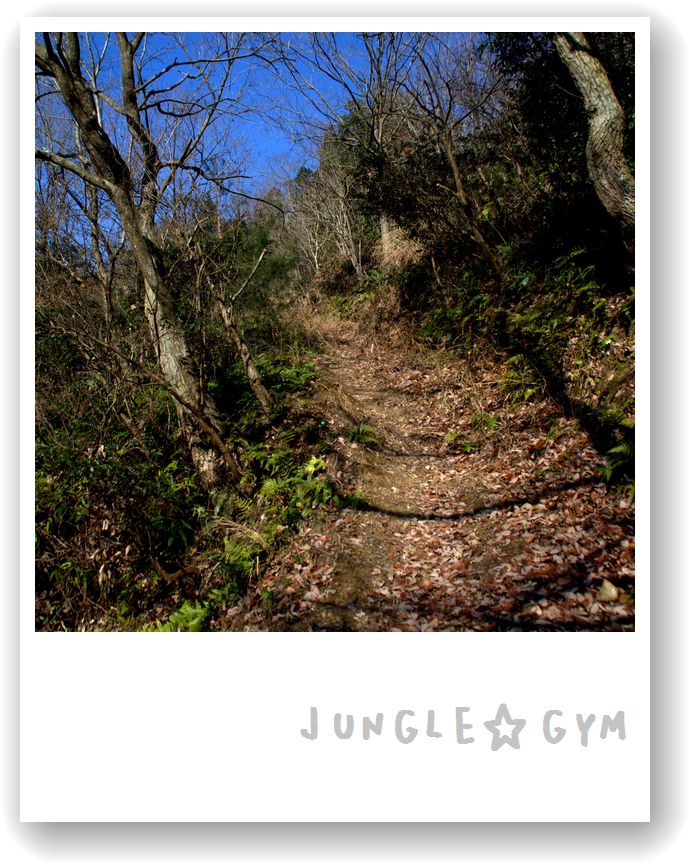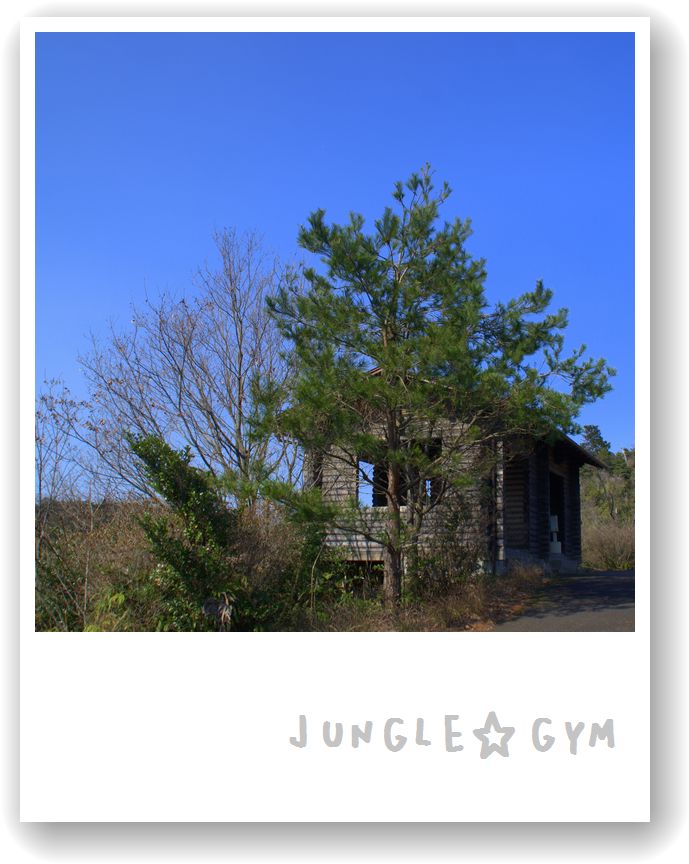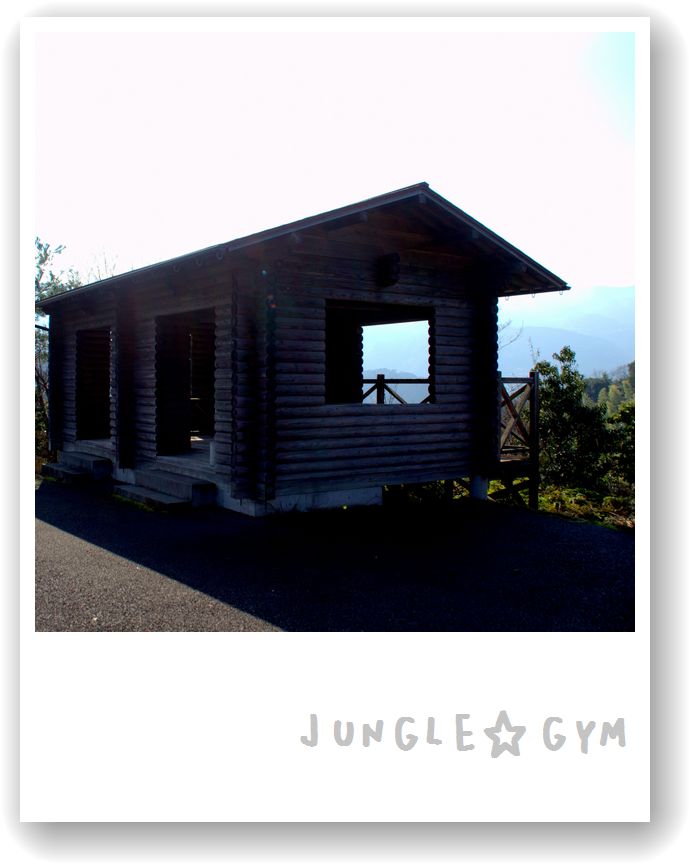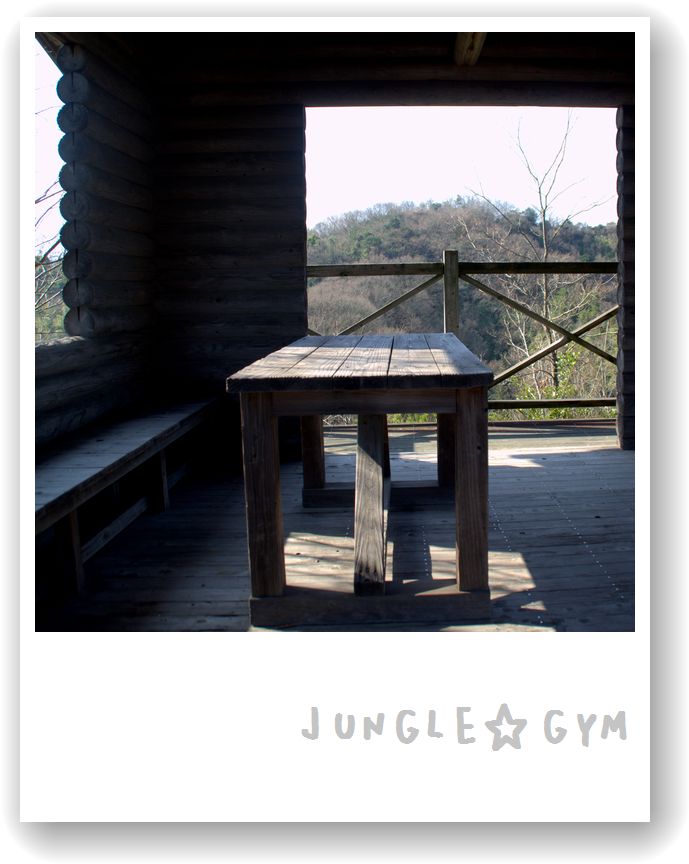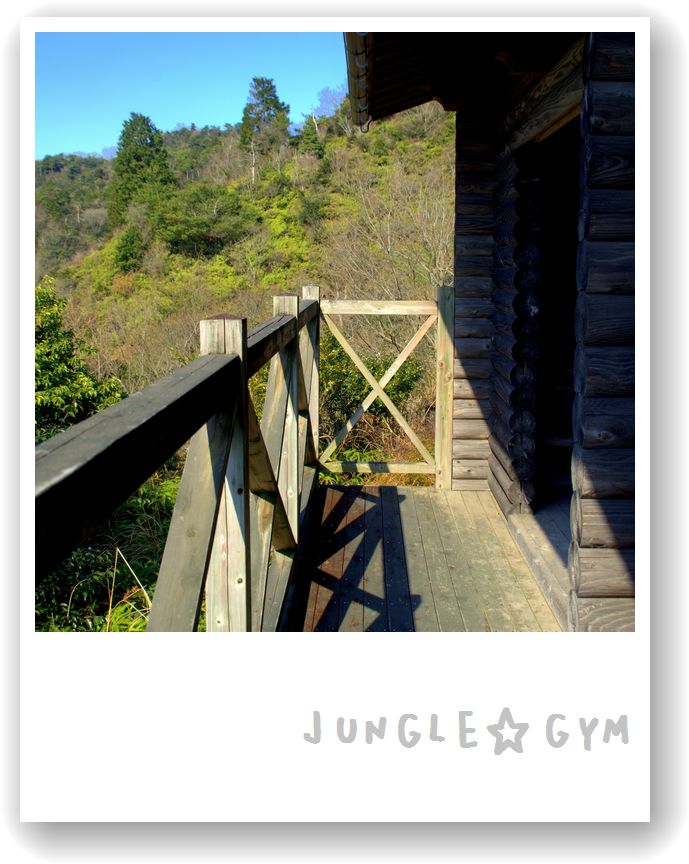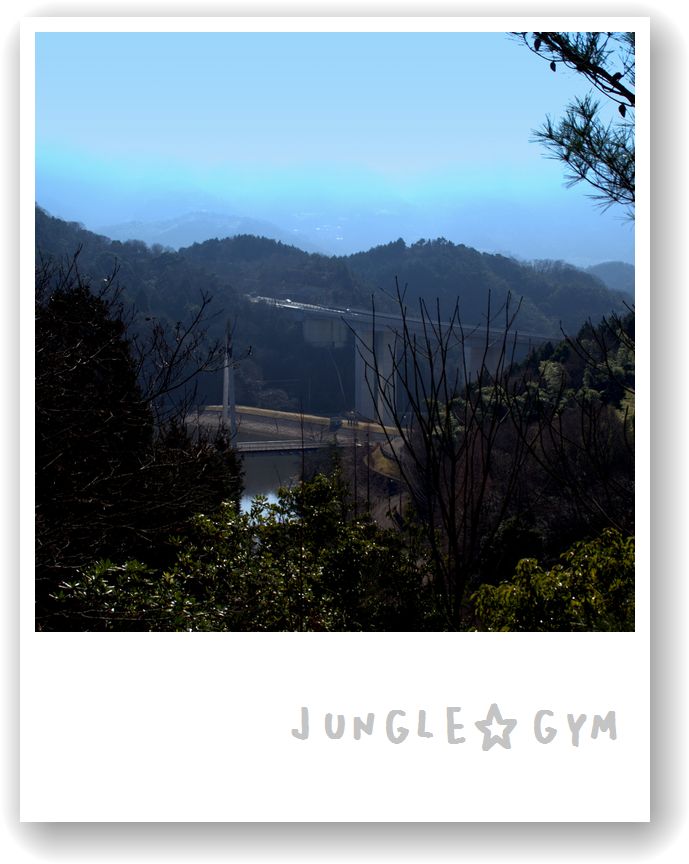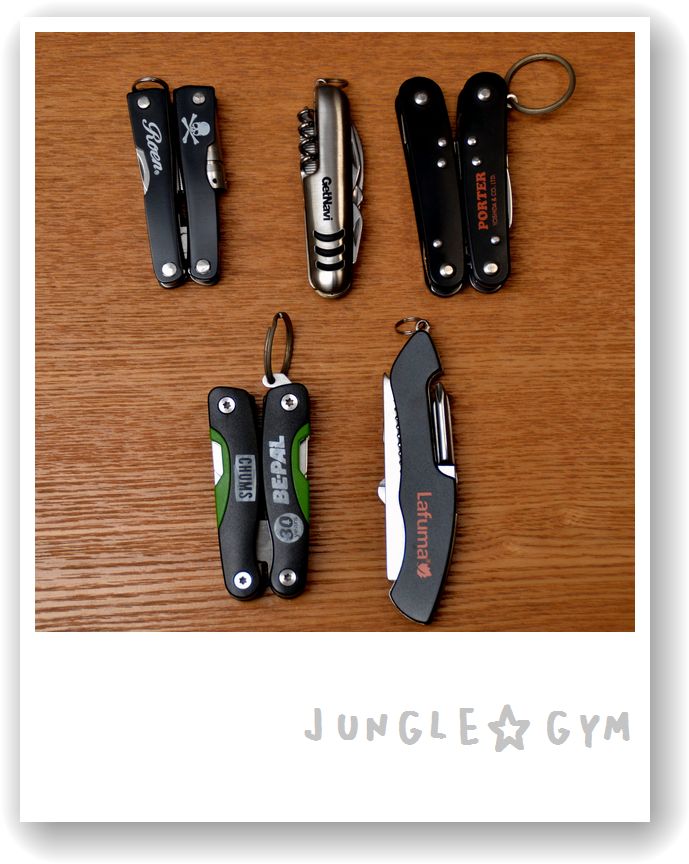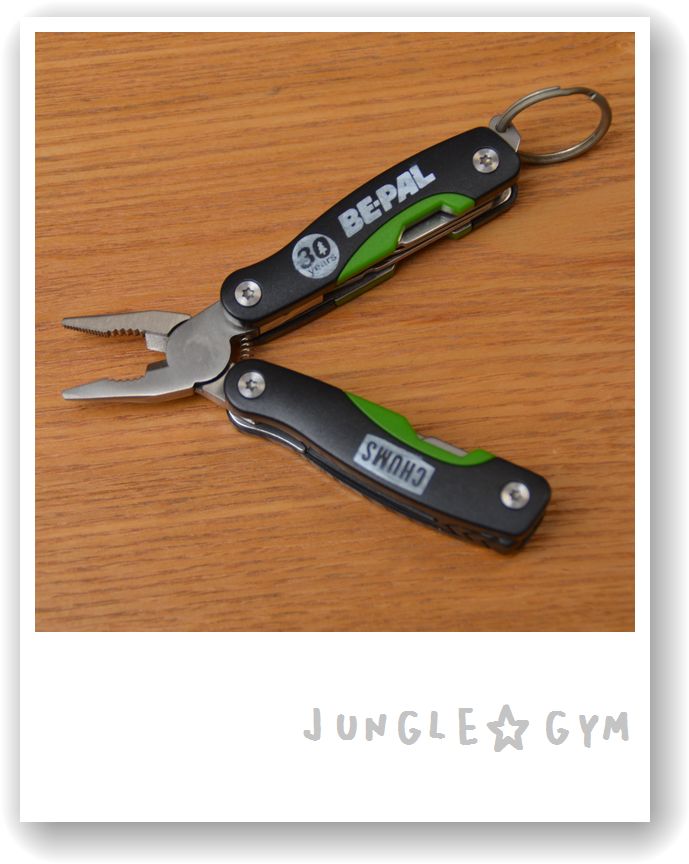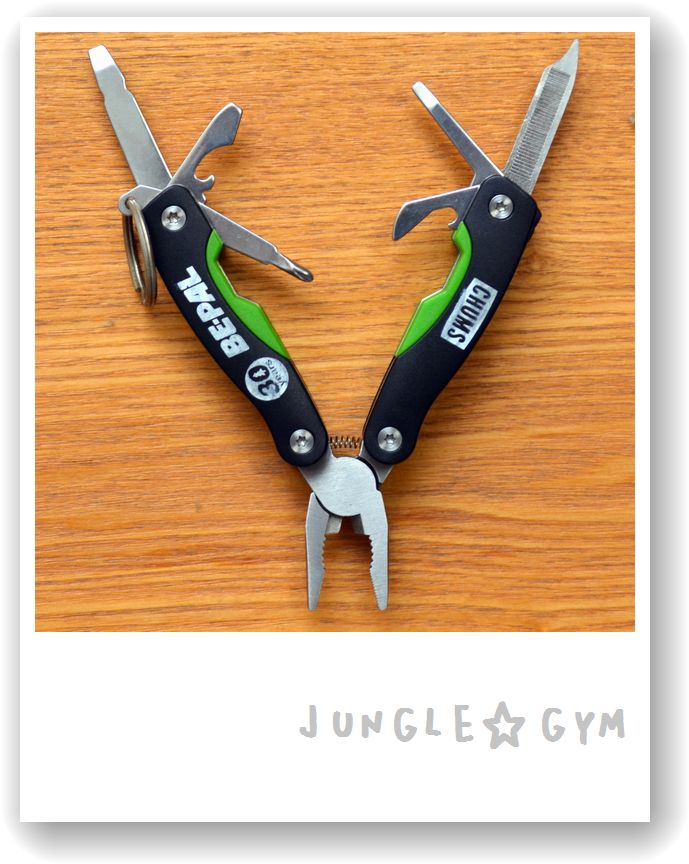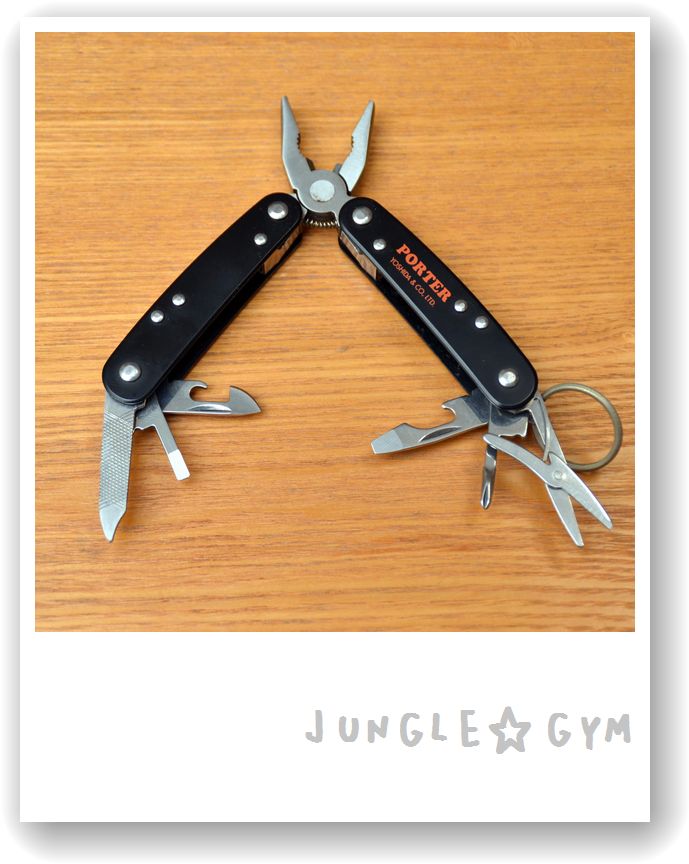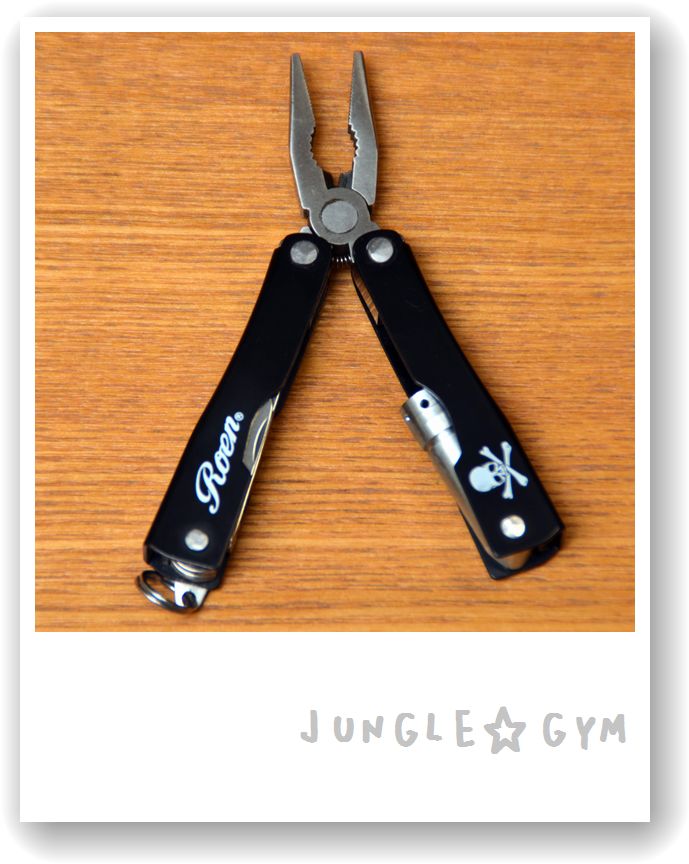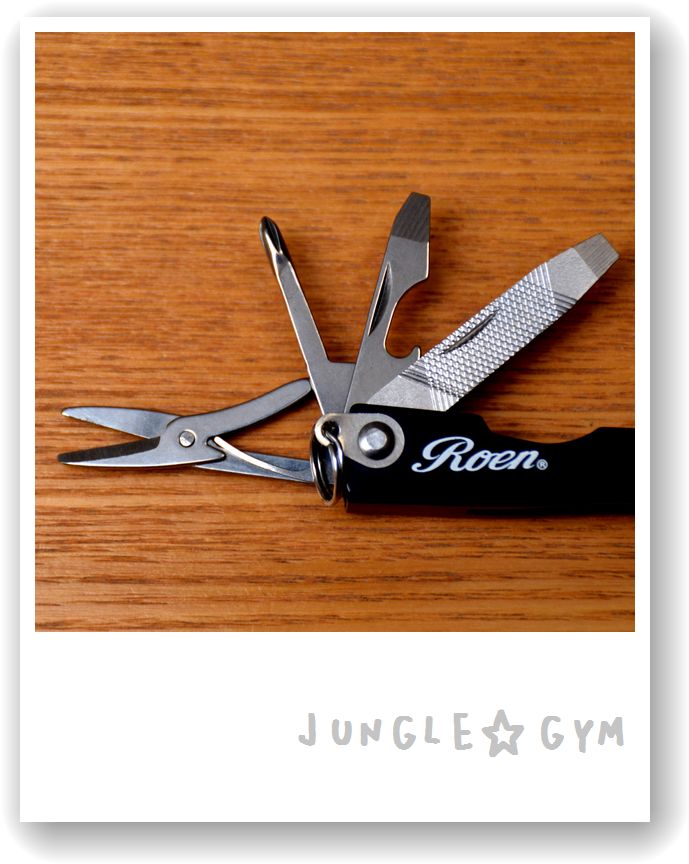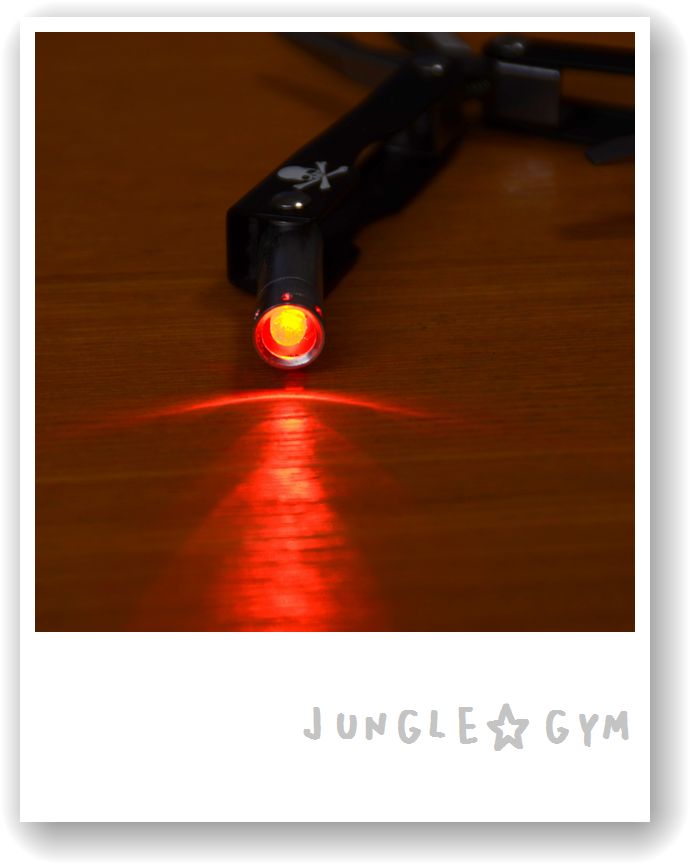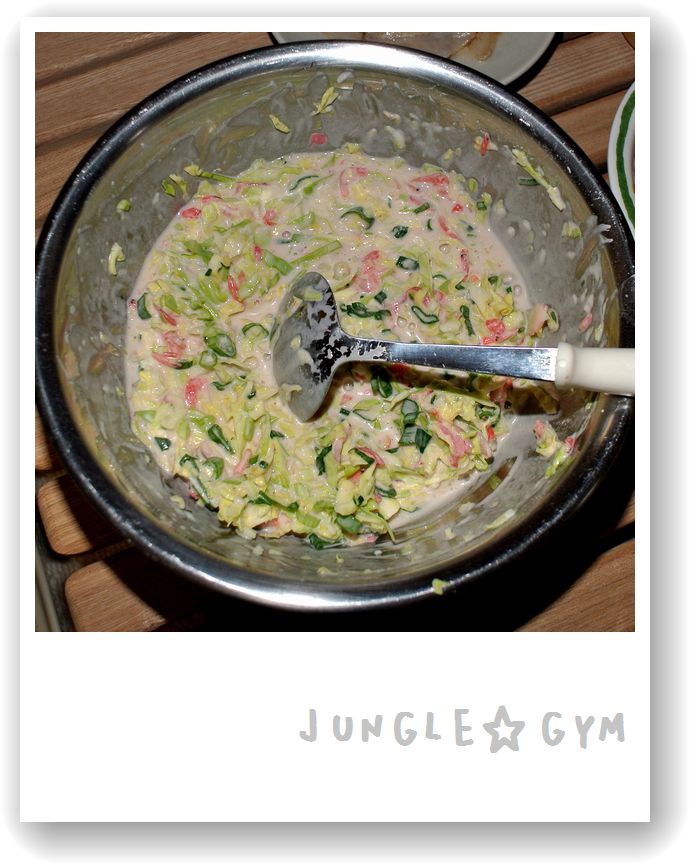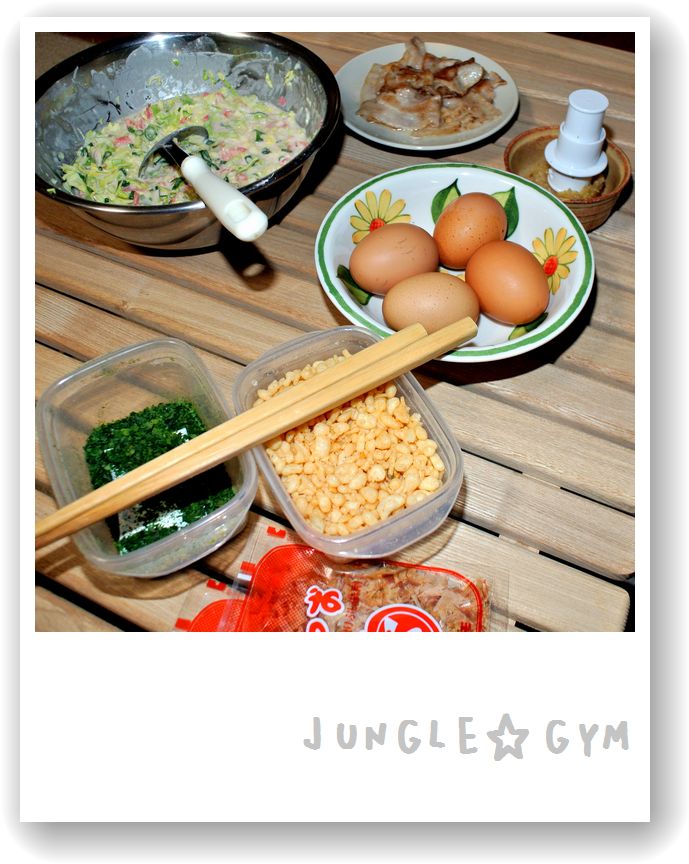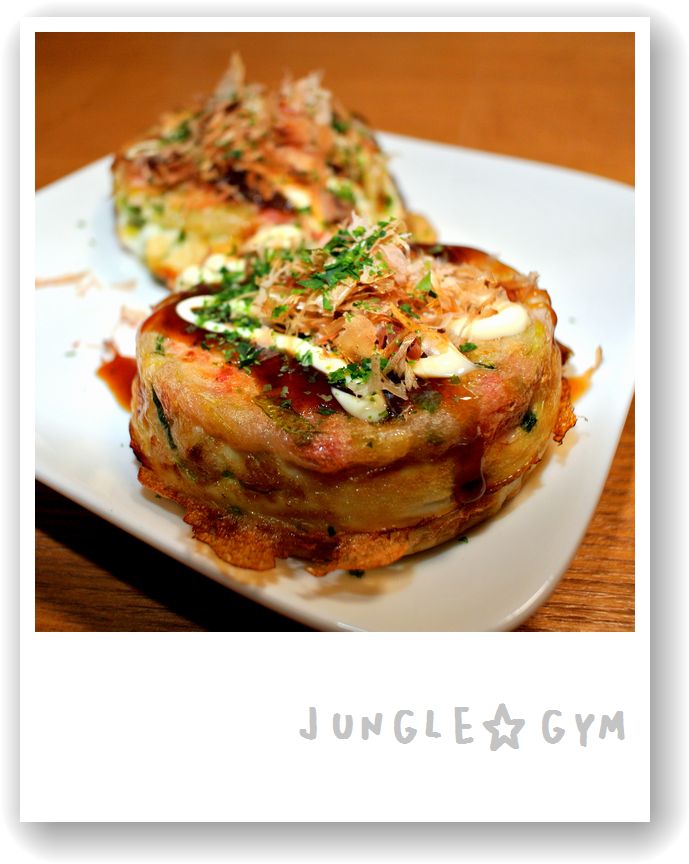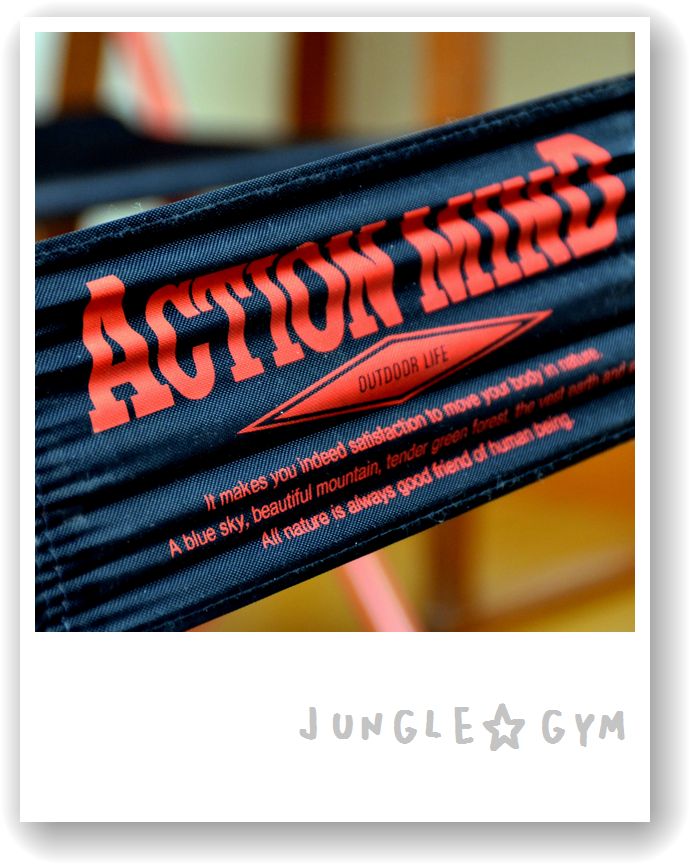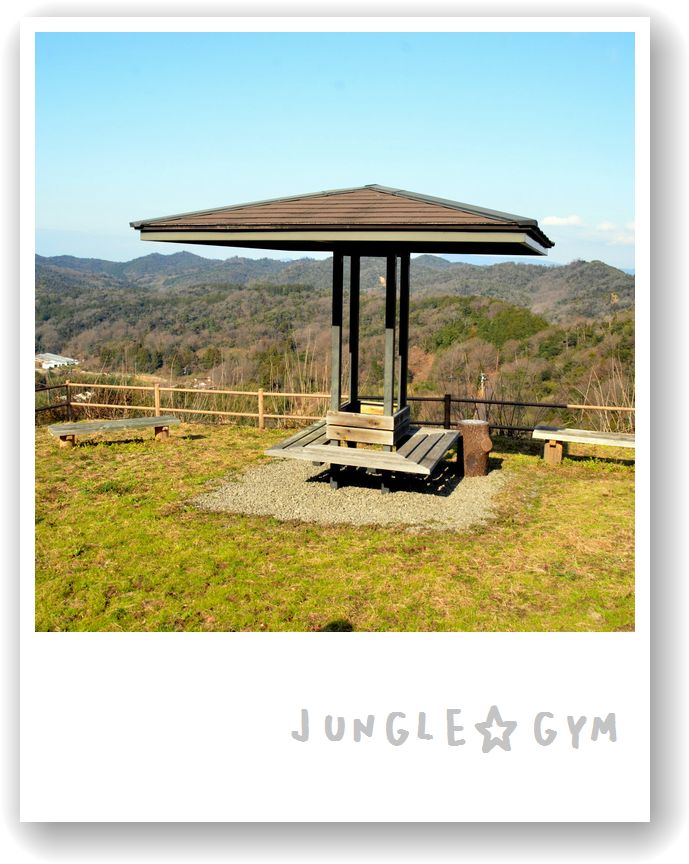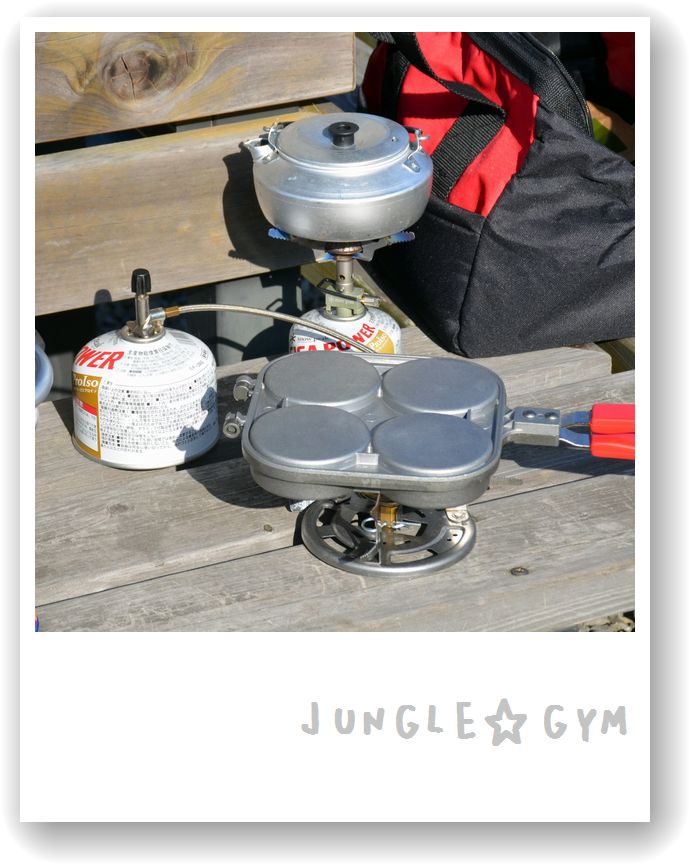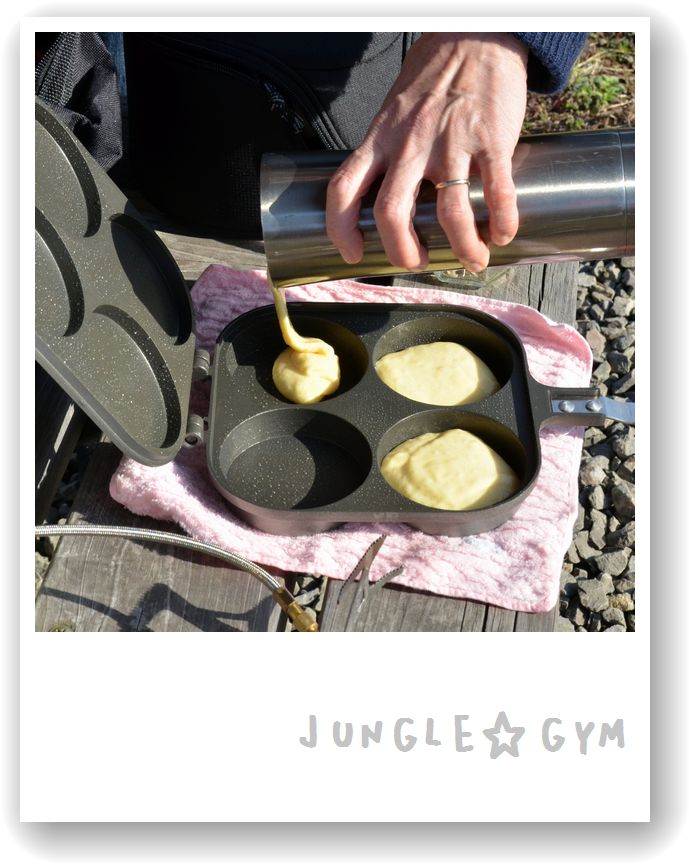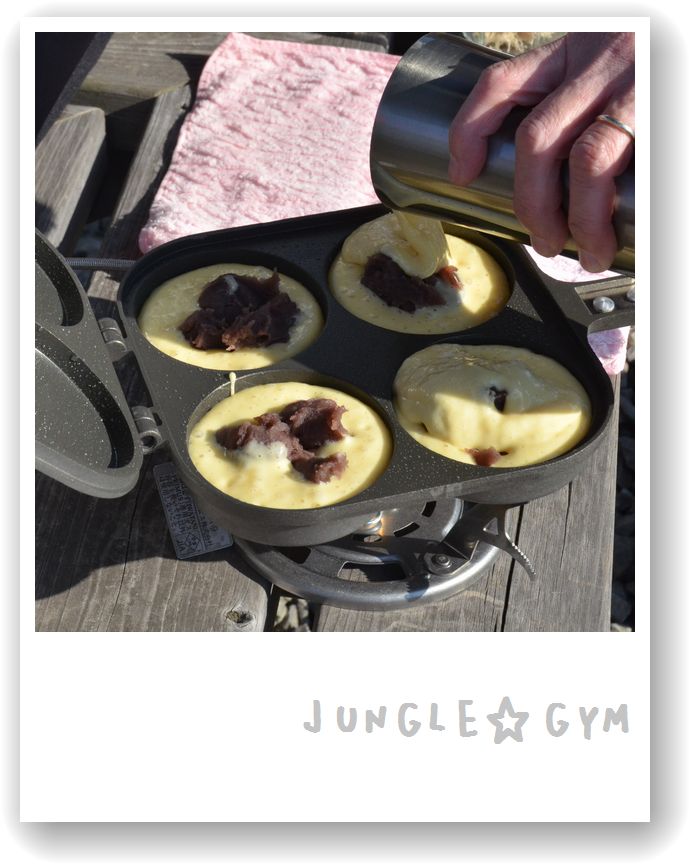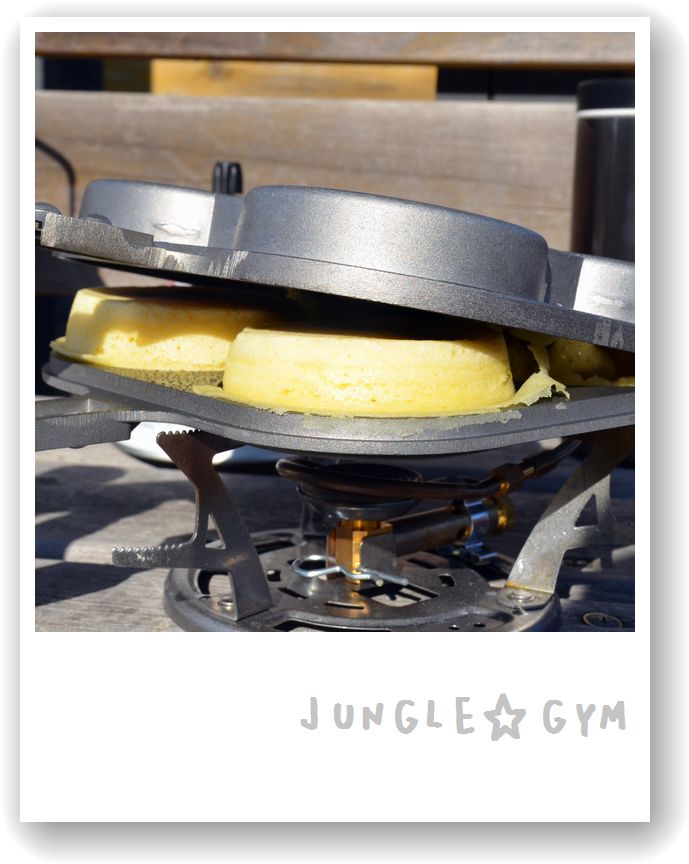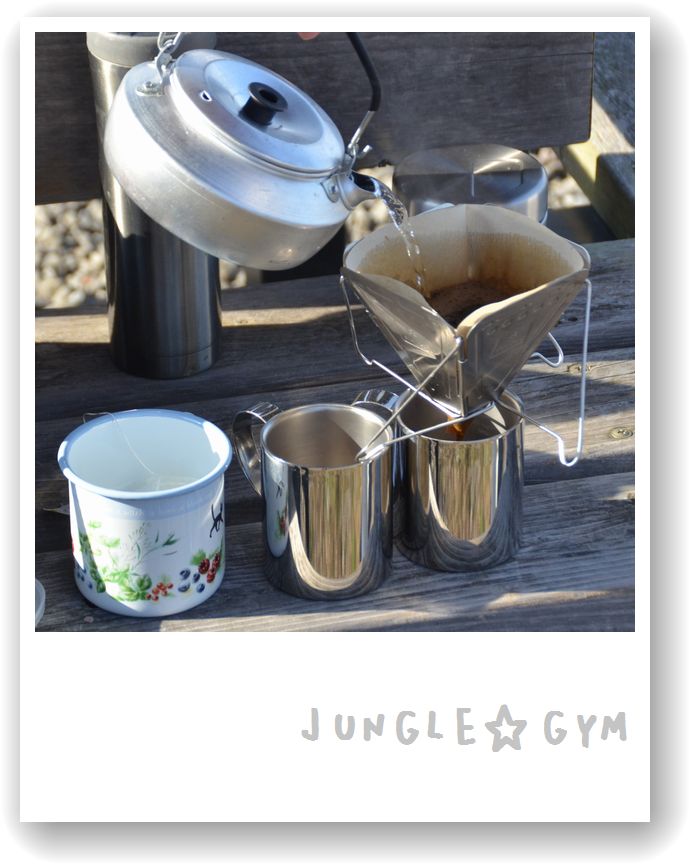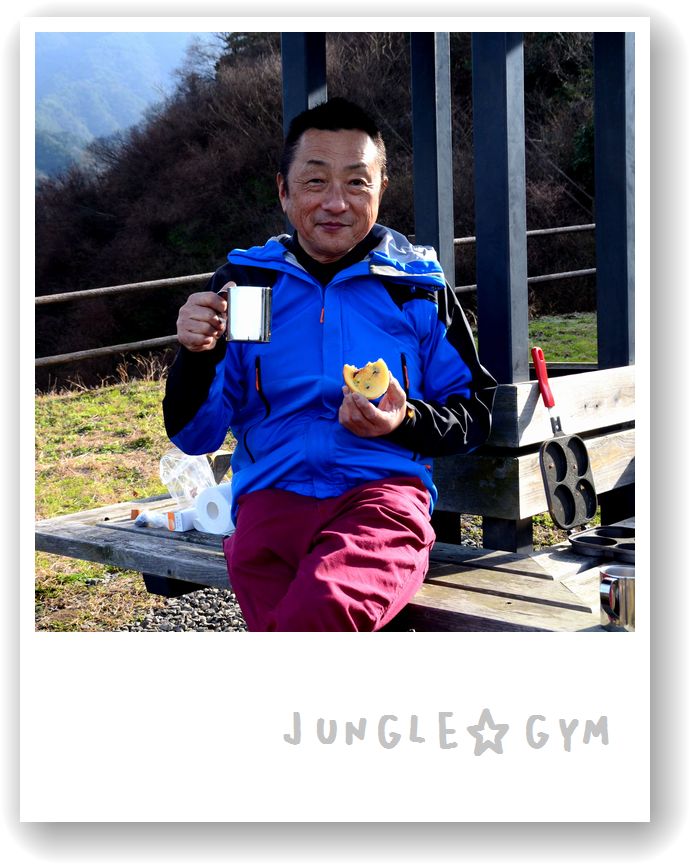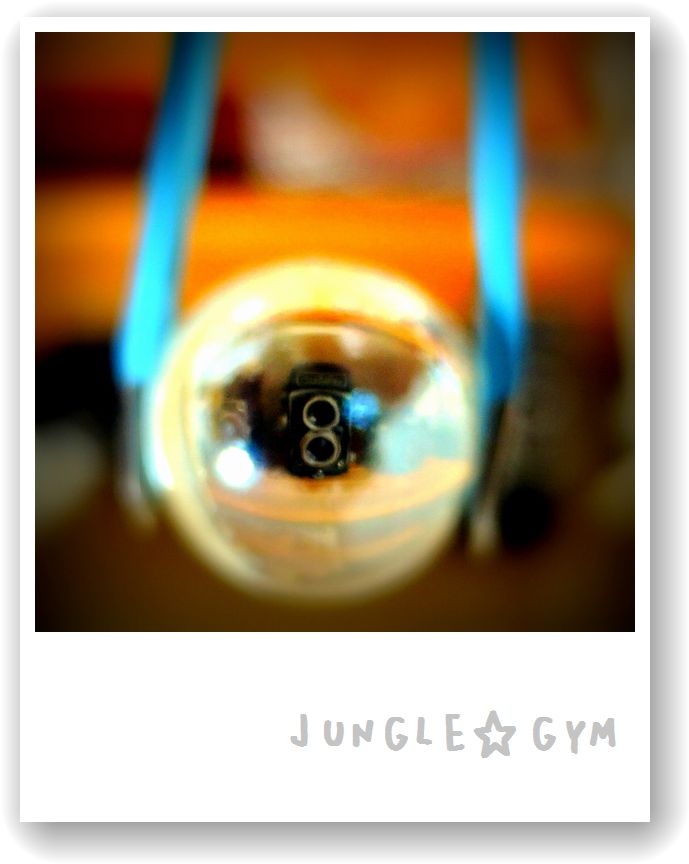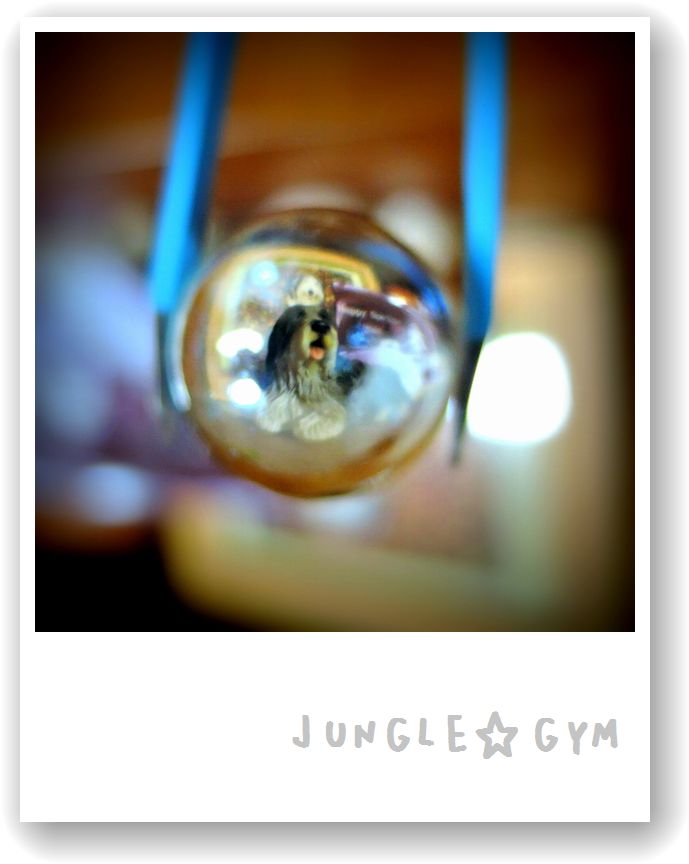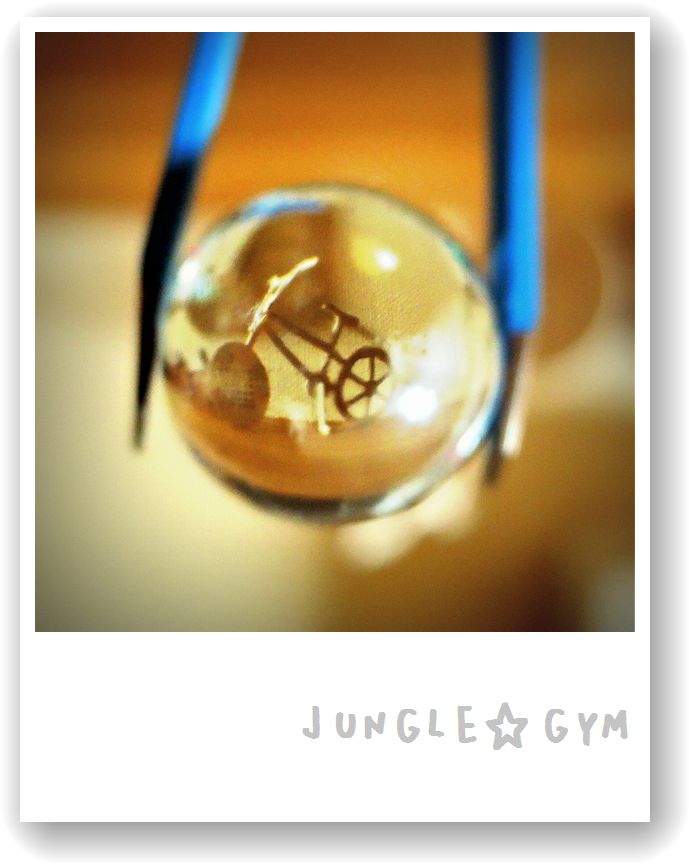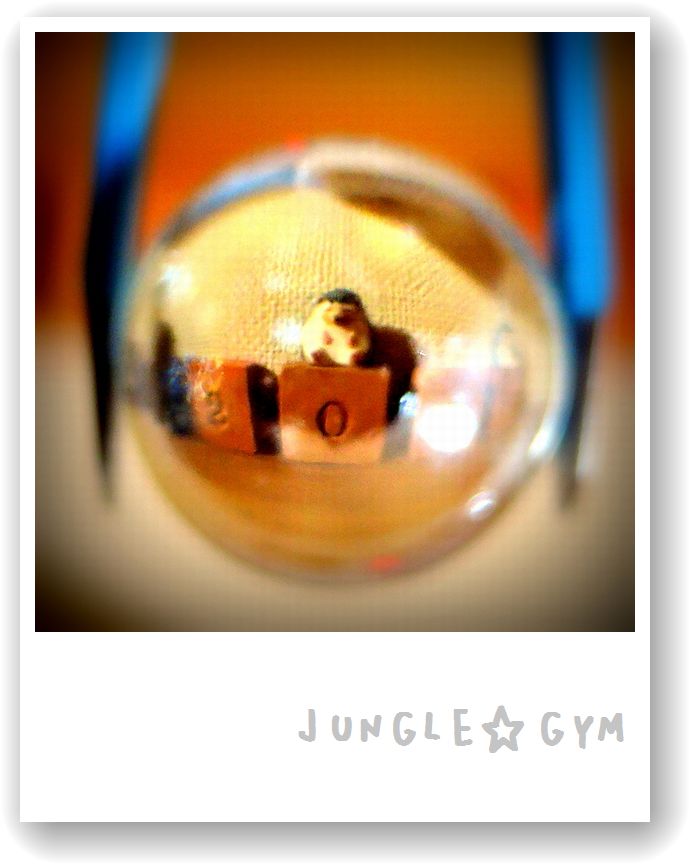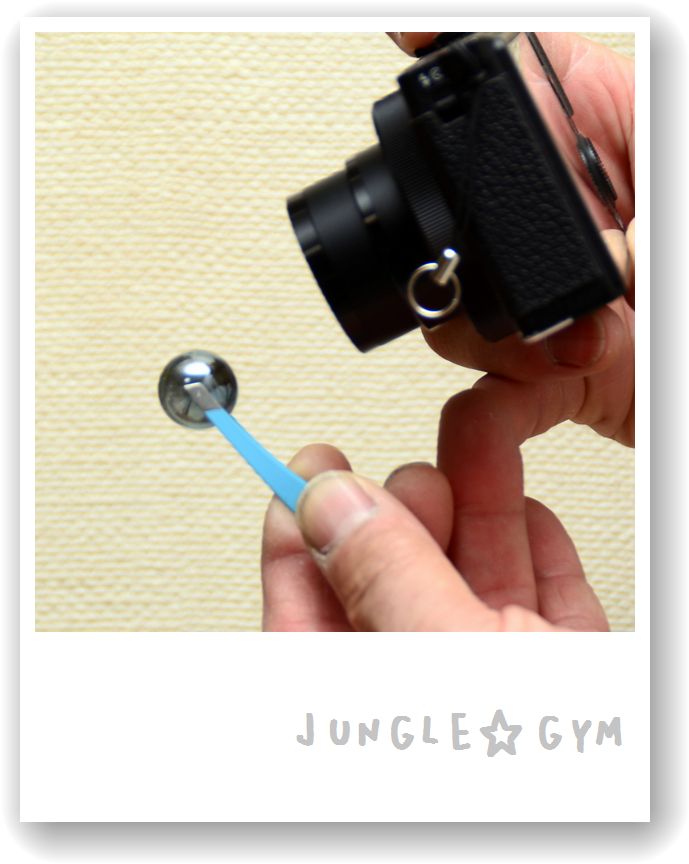友人が、まめに足を運ぶうどん屋があって、
以前から気になっていました。
しかも、それが讃岐ではなく、
西条市の丹原ですよ。
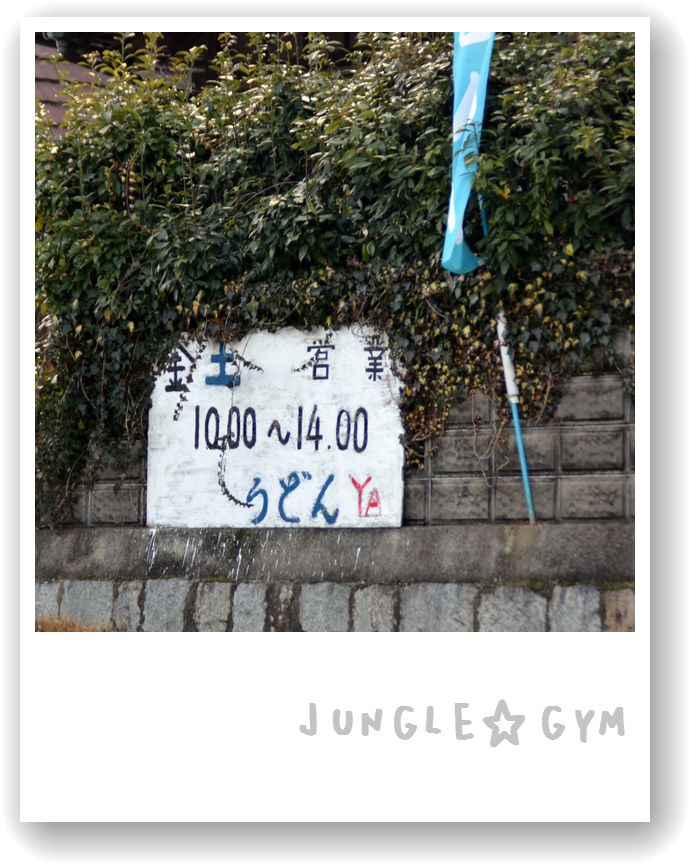
ところが、金曜と土曜しか営業していないのです。
いきなり、ハードル高いでしょう?
ご近所さんでなければ、なかなか来られない。
念願叶って、ようやく土曜日に来ることが出来ました。
2時までの営業時間の所、
1時半に到着。。。ギリギリセーフです。
そのうどん屋の名前は、「うどんYA」
ラッパーみたいな、若者がやっているのか?
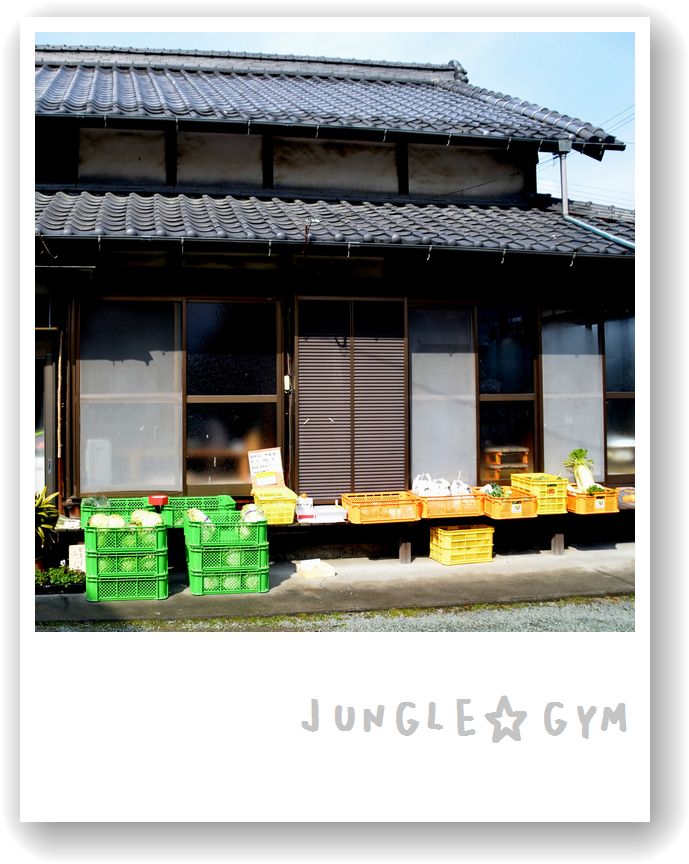
ナビを頼りにやってくると、
最後の最後に、車一台がやっと通れる狭い農道を、
しかもクランクを、クネット曲がって、ようやく到着。
そこは、昔ながらの農家の佇まい。
軒先には、産地直送の野菜が並んでいます。
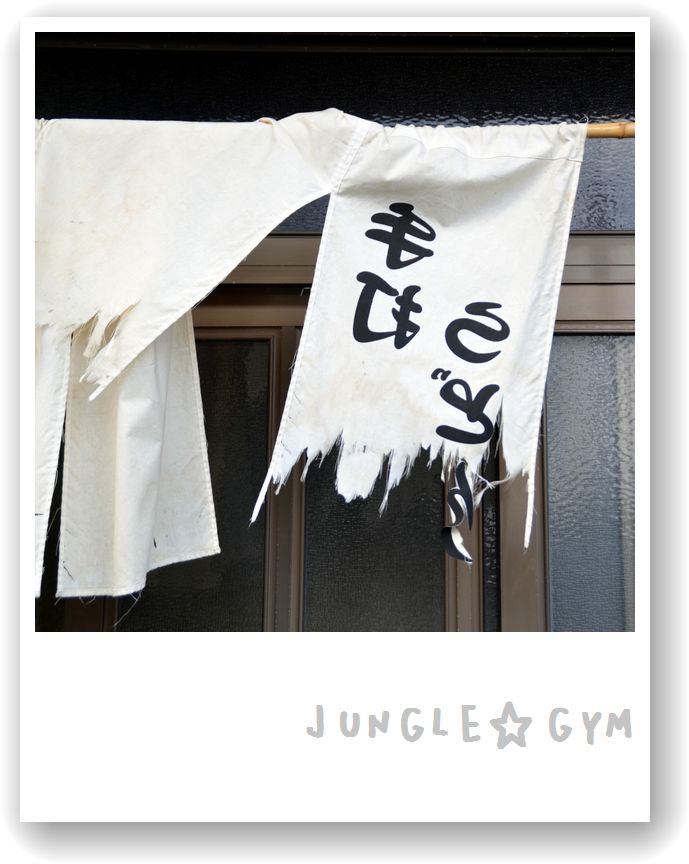
さあ、お店に入ってみましょう。。。。
と!、のれんをくぐろうとすると、
なんと、のれんが素晴らしくボロボロ。
ボロボロですが、綺麗なんです。
ちゃんと洗濯はされていて、アイロンもあたっている。
しかし、その姿はかなり哀れ。
店の歴史の象徴として、あえてこのまま
使い続けて居るのでしょうか?
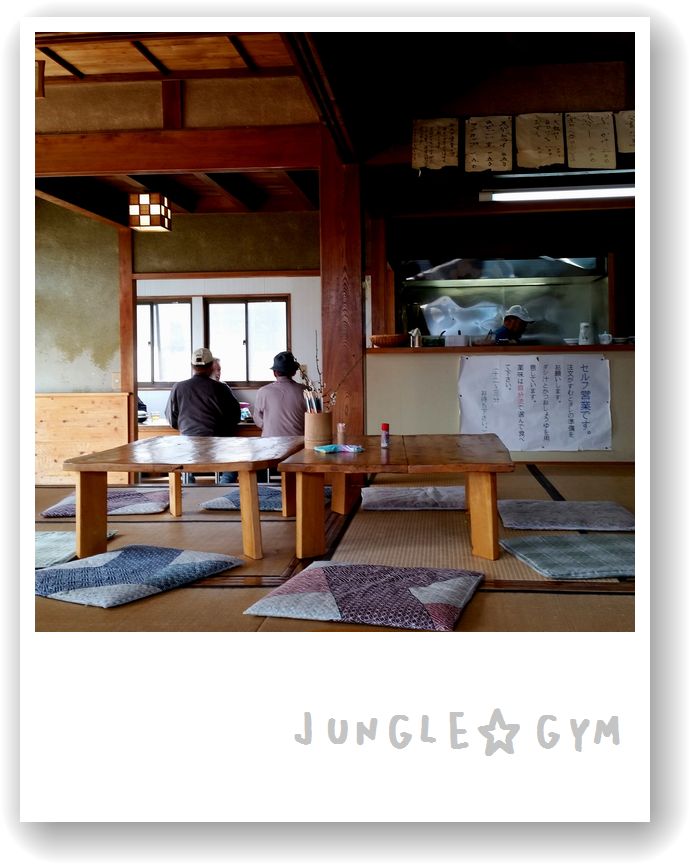
店内に入ると、そこは、農家の居間そのもの。
田舎の親戚の家に、お呼ばれに来たみたい。
お店のスタッフは、調理場に二人。
まあまあのおっさん。
決して、ラッパーではないようだ。
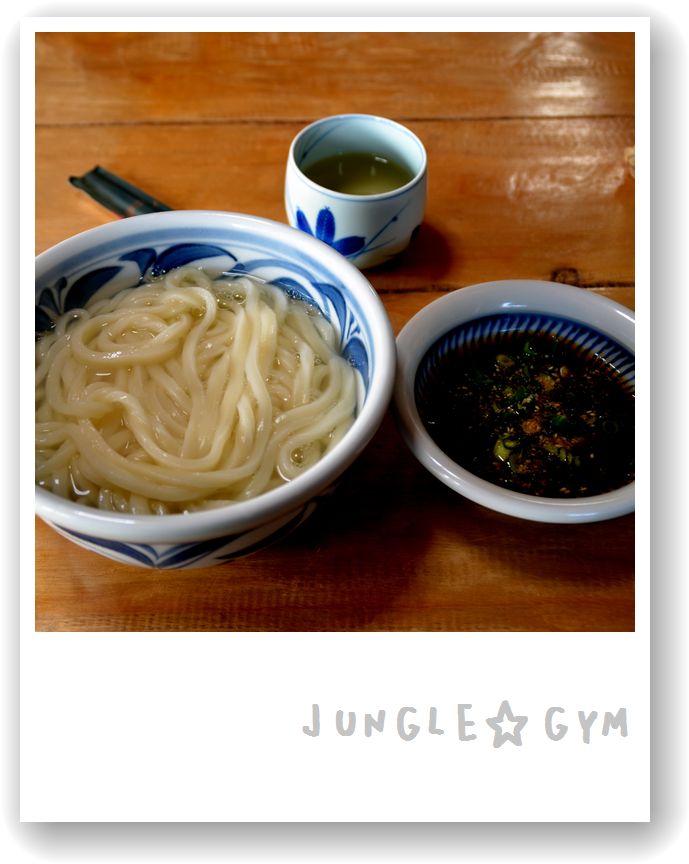
先ずは、初心者ですから釜揚げから。。。
釜からうどんが上がるタイミングを見計らって、
つけダレを、自分で準備します。
ごまや、天カスなど、好みでブレンドします。
小を注文したのに、このボリューム。
そして、これで200円。
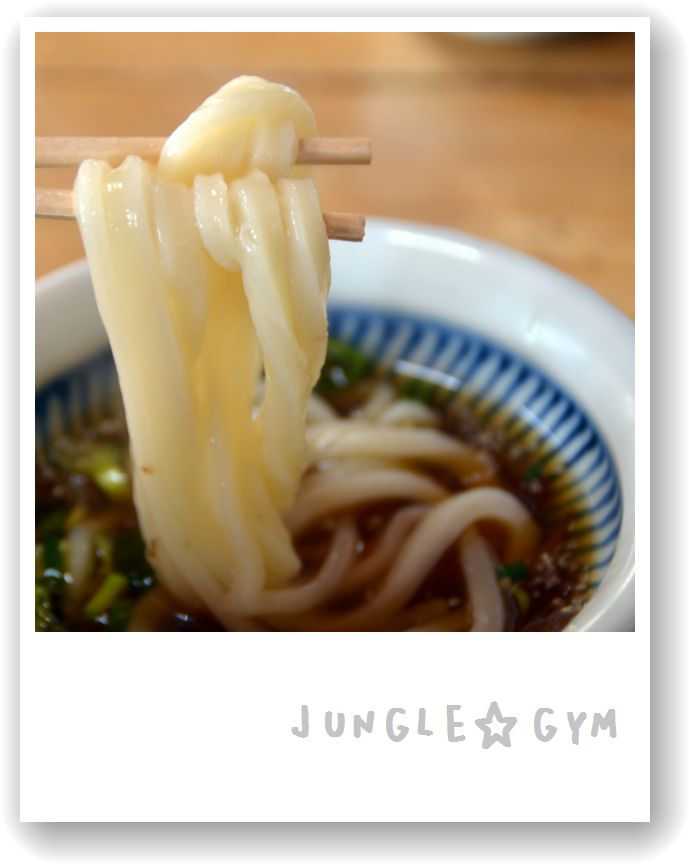
麺はツヤツヤ。
ツヤツヤですが、シコシコ。
のどごしが抜群に良い。
小の割には多いなと思ったけれど、
どこに入ったのかわからないくらい、
するするっと流し込んでしまいました。
これは美味い!!!
リピート決定!!!

さて、お会計はこのザルですよ。
自分で放り込んで、なんならお釣りも自分で取ります。
なんという自由な空気でしょう。
おいちゃんに、「美味しかった、ごちそうさん」と言うと、
「もっと早よう、来い」と言われました。
はい、そうしますYO。