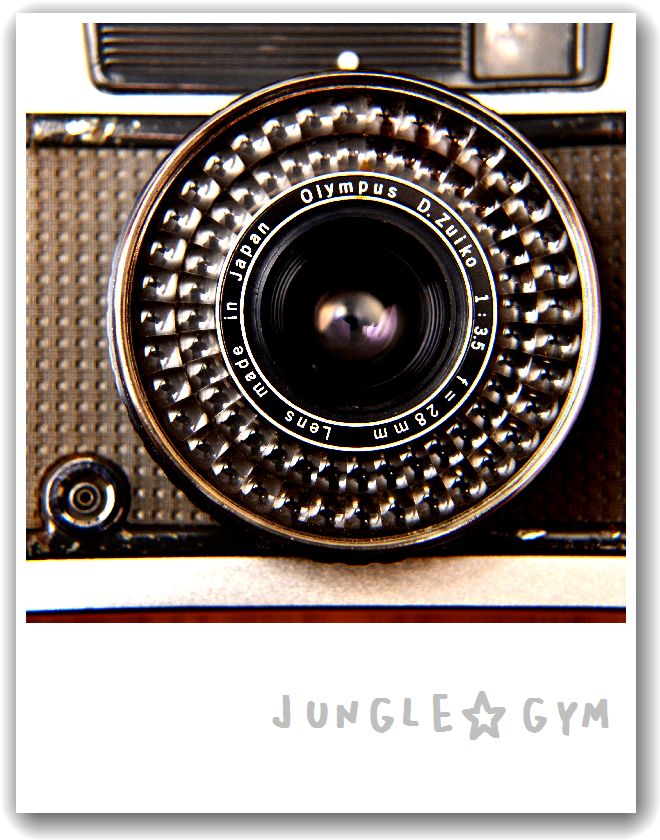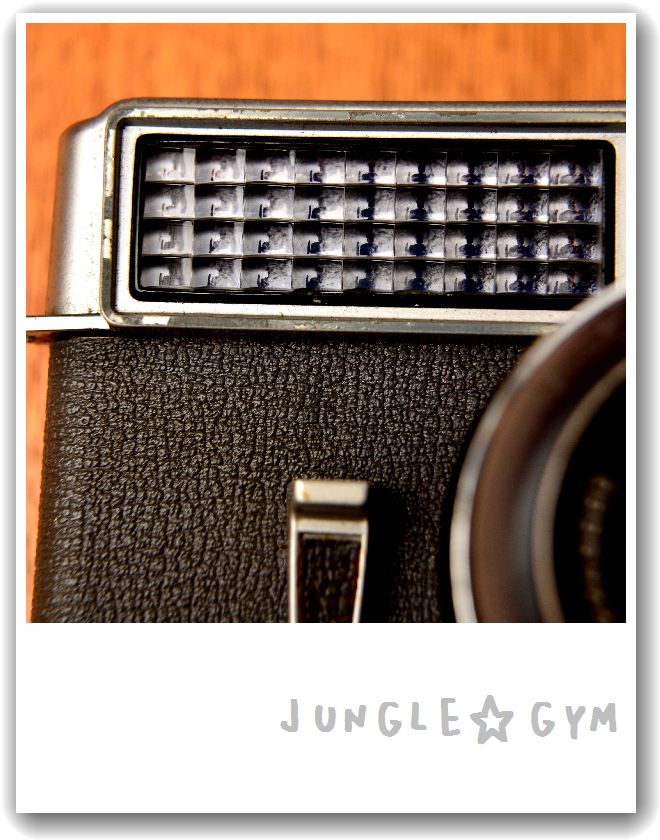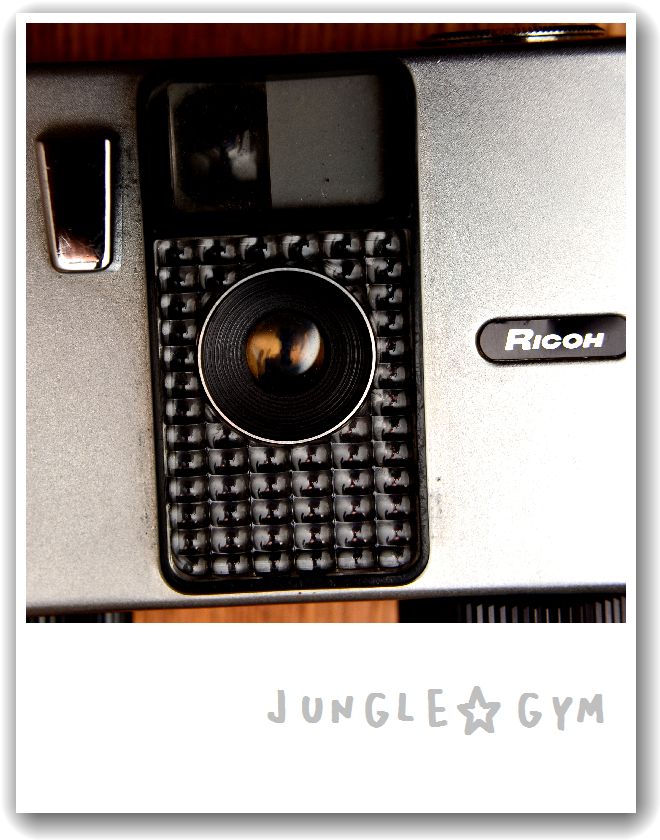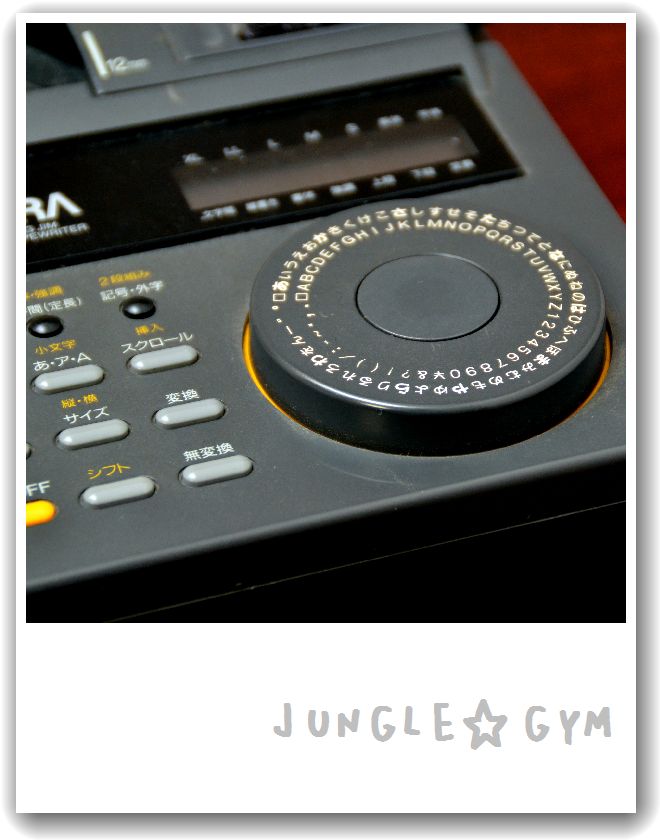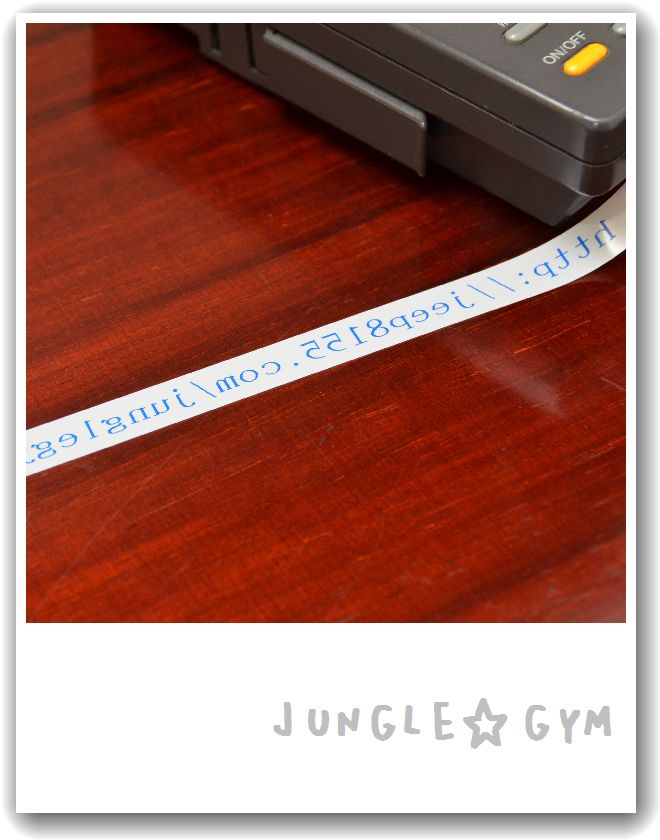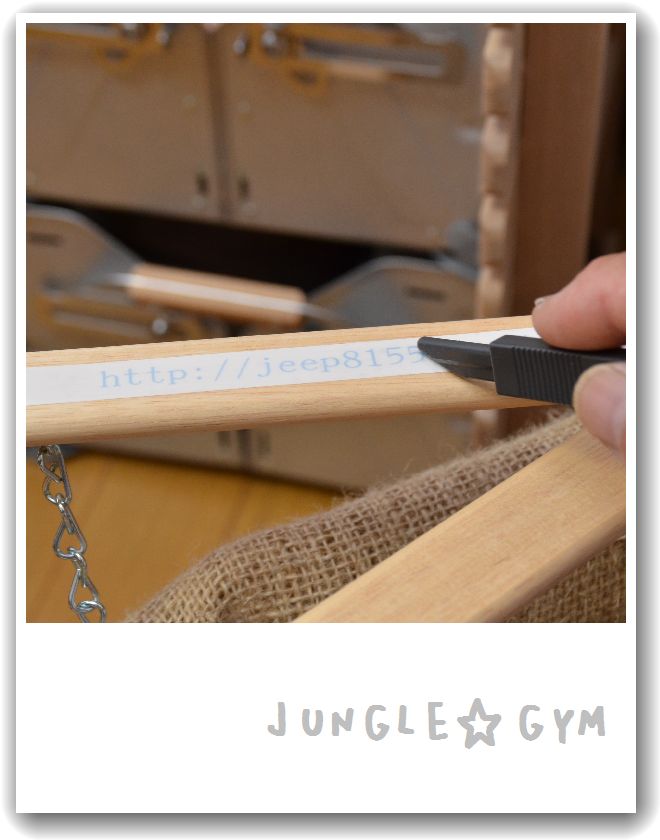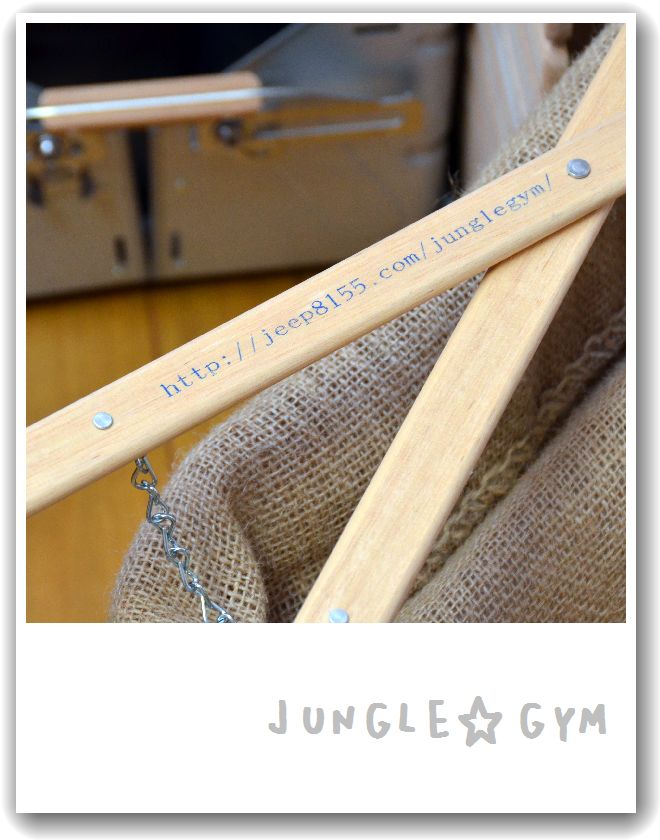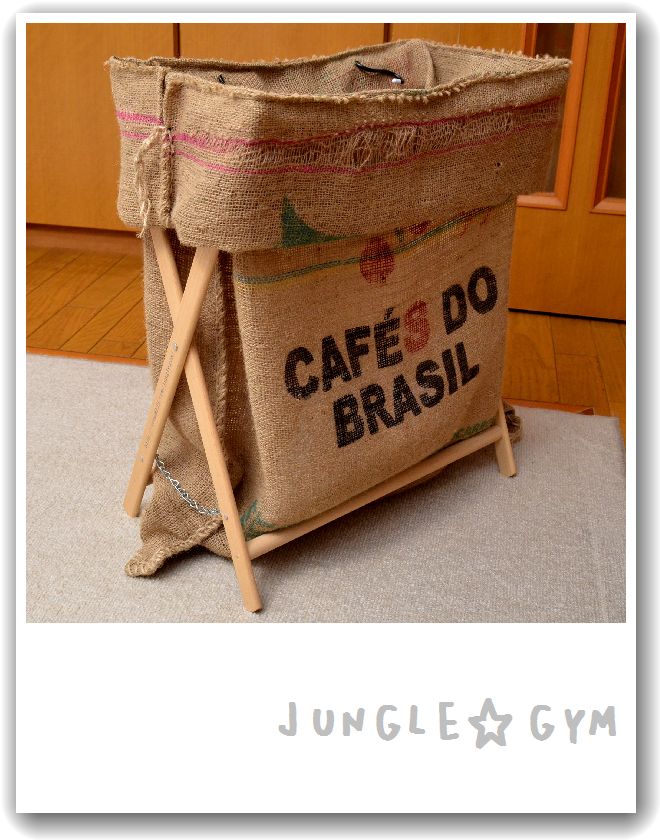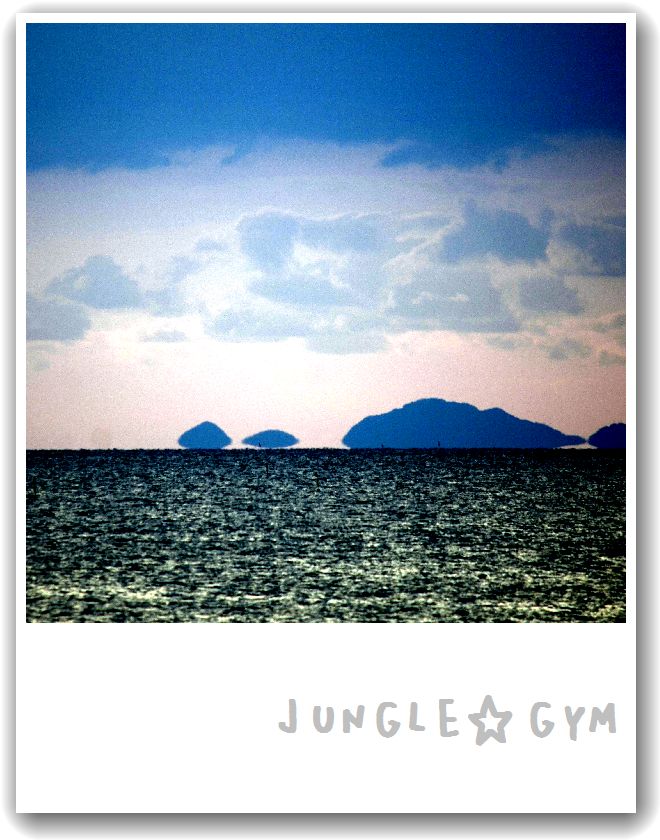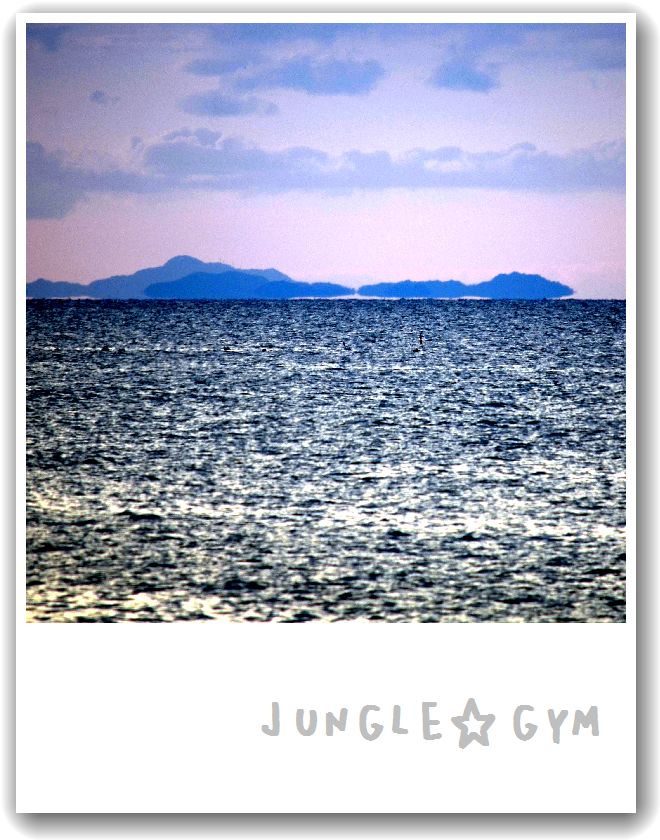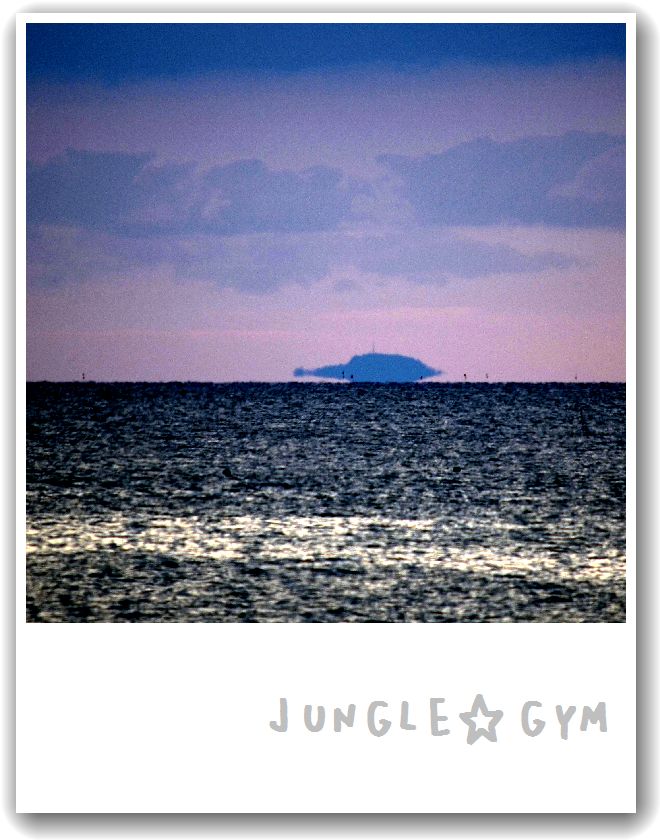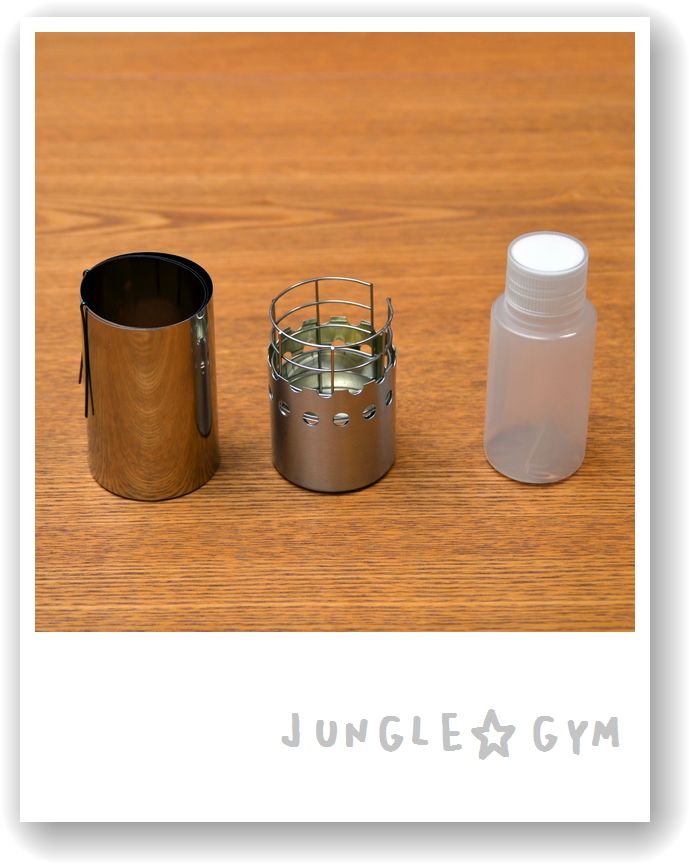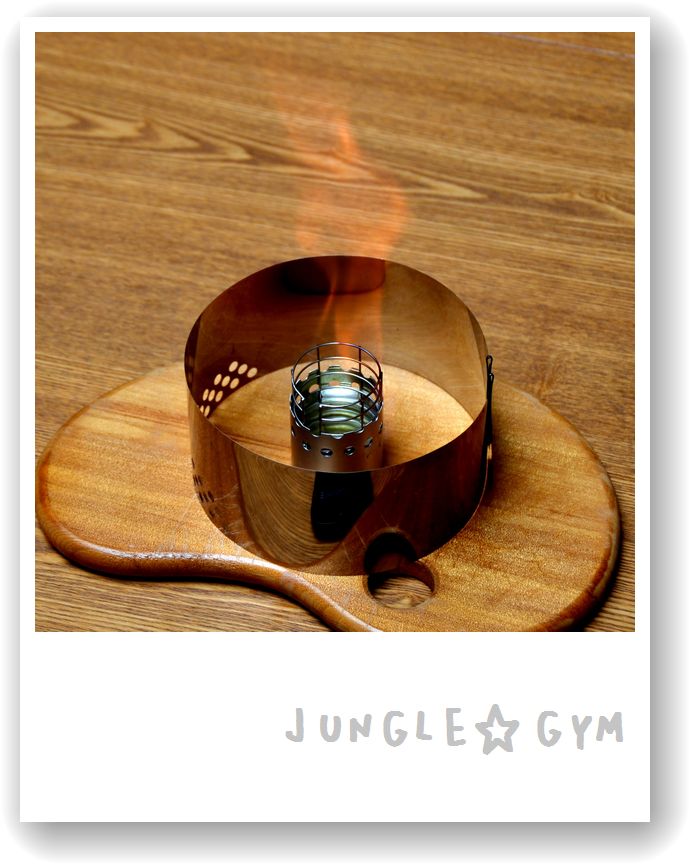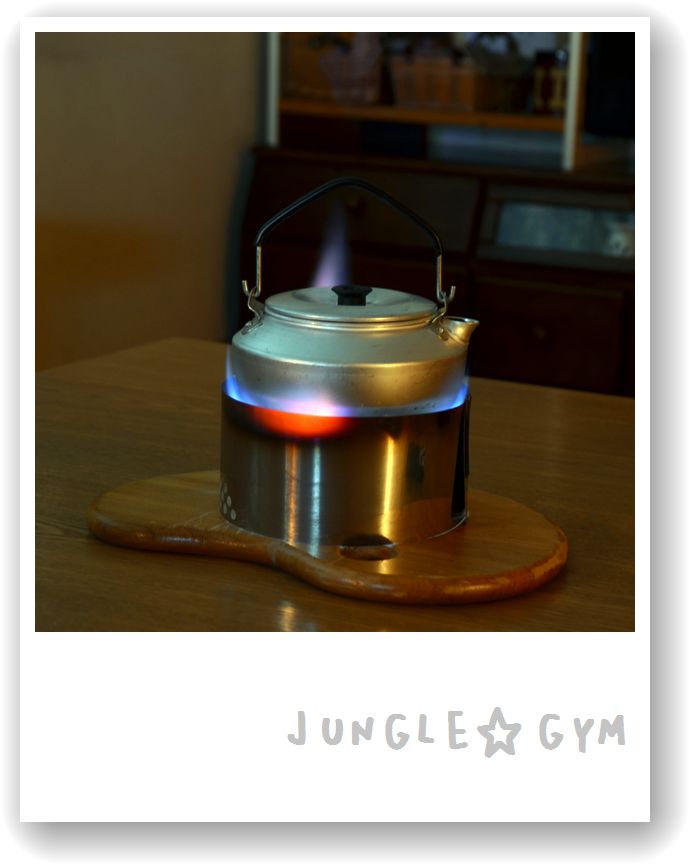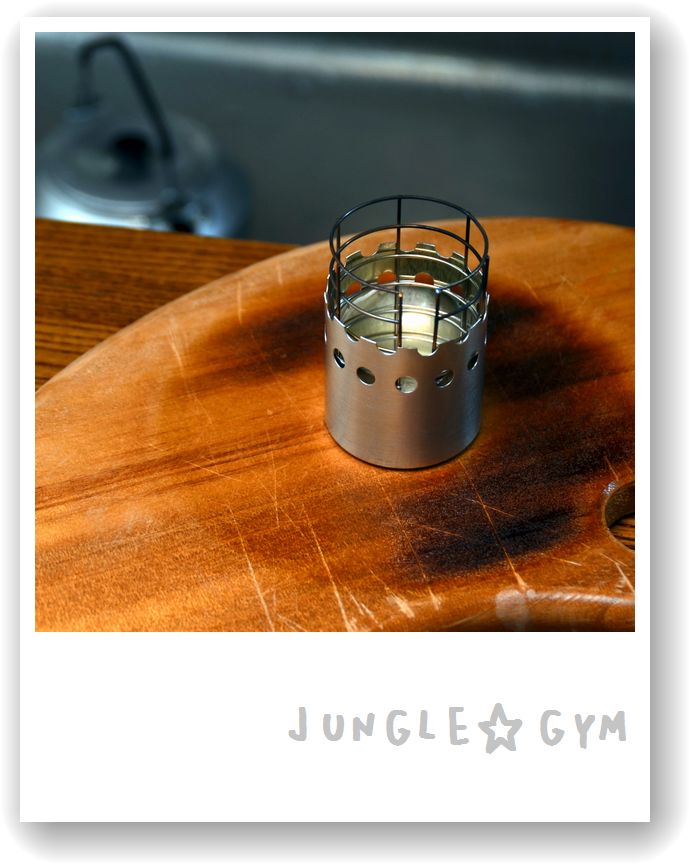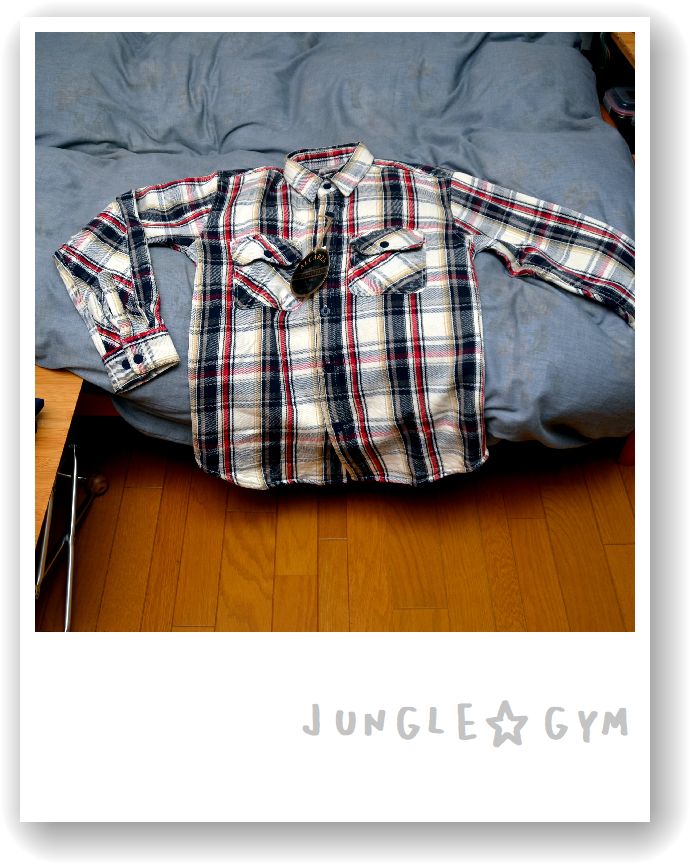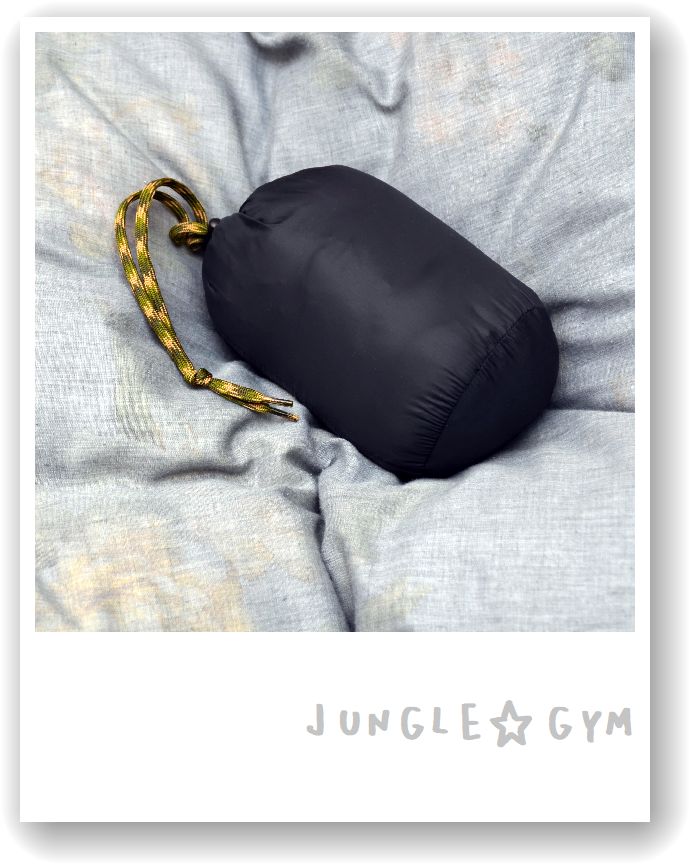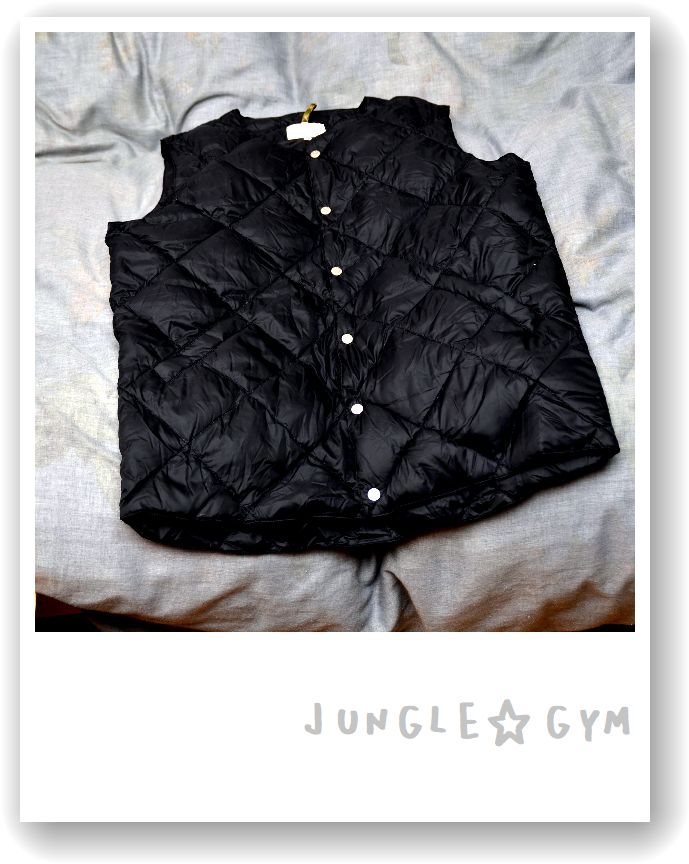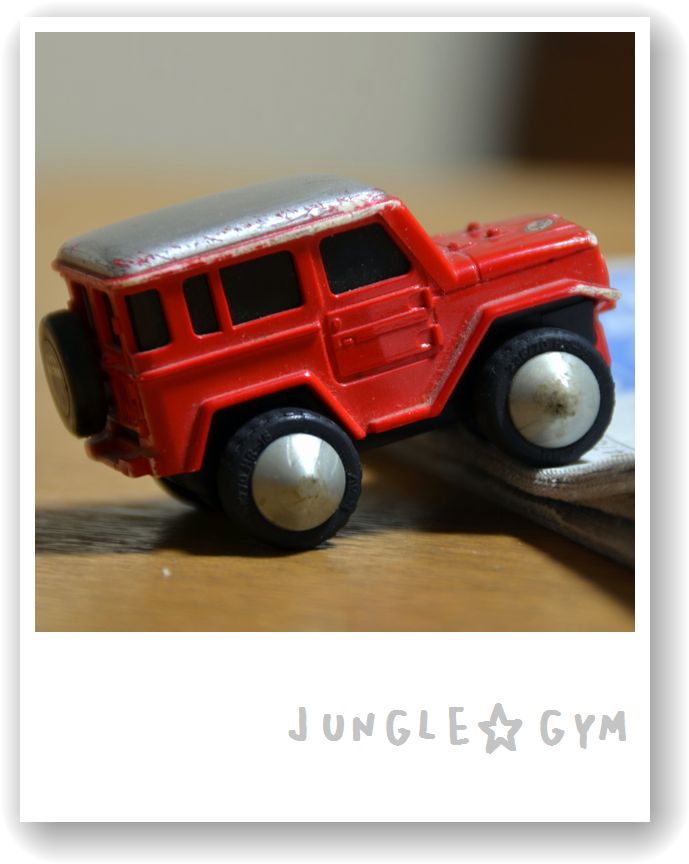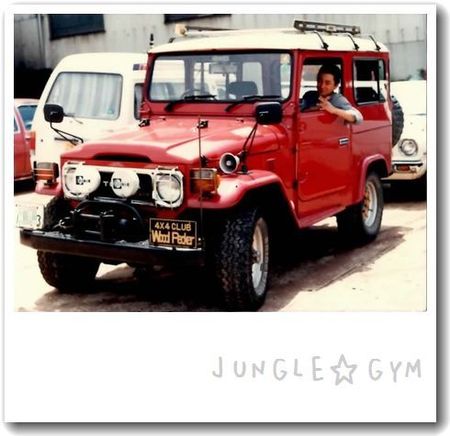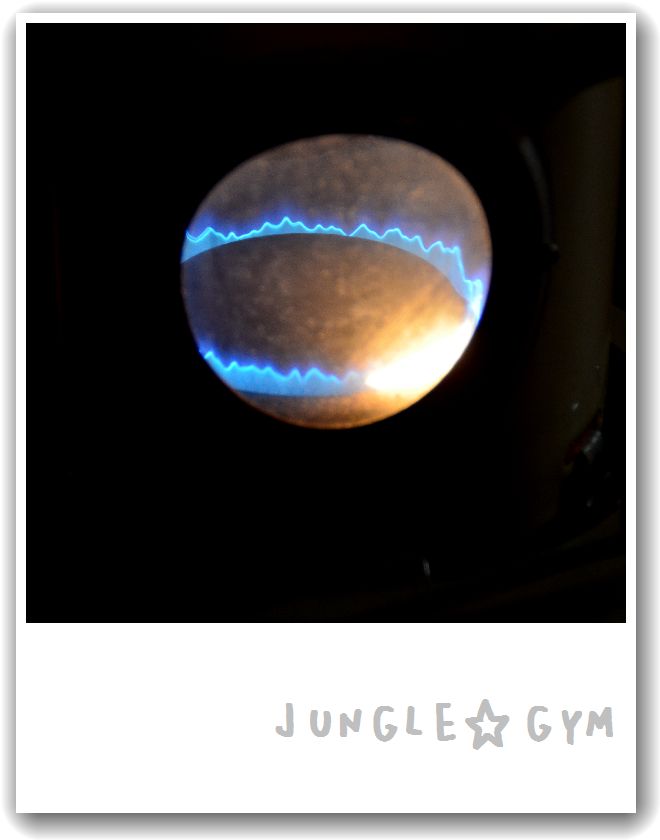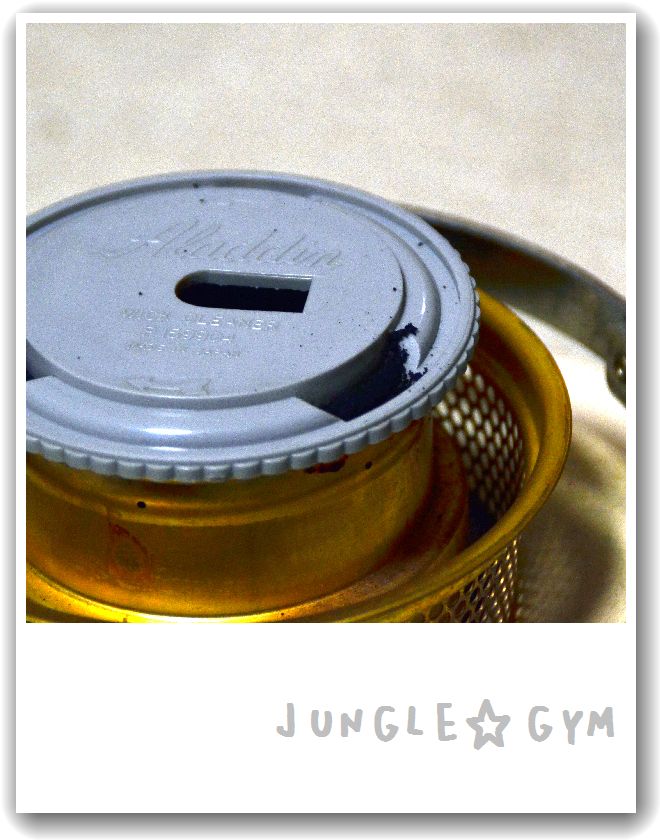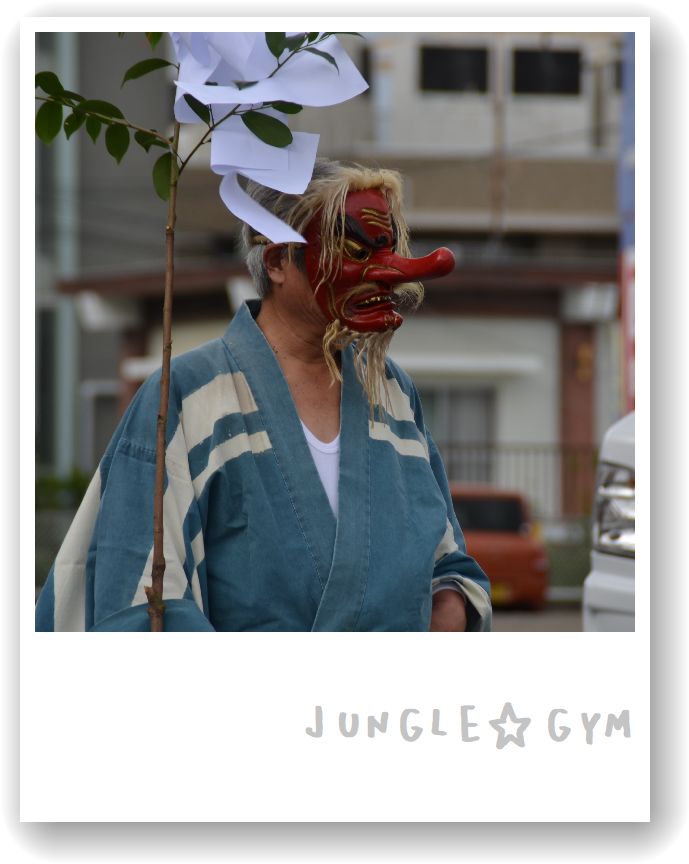再生可能エネルギーの主力として、
太陽光発電が、どんどん展開されていますね。
今から40年ほど前のカメラにも、
その原型となるシステムが取り入れられていました。
それが、セレン電池式露出計です。
セレンという物質に光起電効果があって、
また日本でも比較的多く産出されたこともあり、
かつてEEといわれる自動露出カメラの中に
セレンを用いた光電池が多く使用されました。
このカメラは、オリンパス・ペンEE
レンズの周りのキラキラした部分が、
セレン電池が内蔵されているところです。
今の太陽電池に比べると
ずいぶん起電力が弱いので、
レンズで集光するようになっています。
ビジュアル的に、このキラキラの部分が
カメラのデザインのアクセントになって、
ノスタルジックカメラマニアの中でも、
このキラキラカメラを好んで収集する人もいますよ。
セレン電池の起電力を利用するので、
別に電池を入れる必要はありません。
特別にショックを与えていなければ、
経年劣化することは無いので、
今でも使うことが出来ます。
ただ、反応が遅いので
しばし、明るさに馴染むまで
時間を置くほうが良いようです。
これは、セコニックの露出計。
露出計専門のメーカーです。
一時期だけ、セレン電池露出計が発売されていました。
安価に製造できることや、
電池を必要としないというメリットが有りますが、
周辺光の影響を受けやすかったり、
反応が遅いことなどから、
Cd-Sや、SPDに変わっていきました。